Blog 講師ブログ
2025年10月30日
ギターチューニング完全解説|最短で覚える正しい音合わせ

はじめに:チューニングができるとギターがもっと楽しくなる

ギターを始めたばかりの方が最初にぶつかる壁のひとつが、「ギターチューニングのやり方がわからない」という悩みです。どんなに上手に弾いても、チューニングがズレていると音が濁ってしまい、演奏が上達しません。本記事では、初心者でも迷わずできるように、チューナーの使い方や手順、よくあるミスの対処法をわかりやすく解説します。正しいチューニングのやり方を覚えれば、練習がより楽しく、音感も自然に育っていきます。
ギターチューニングとは?なぜ必要なのか

チューニングの意味と役割
ギターチューニングとは、ギターの各弦の音程を基準の高さ(ピッチ)に正確に合わせる作業のことを指します。
ギターは6本の弦それぞれが異なる音を担当しており、それぞれが正しい高さに調整されていないと、コードを弾いたときに音が濁ったり、メロディが不自然に聞こえたりします。
特に初心者の場合、「弾いているのにうまく聴こえない」「動画と同じように弾いても違う音になる」という悩みの多くは、実はチューニングがずれているだけということがほとんどです。
ギターの弦は金属でできているため、わずかな温度や湿度の変化でも伸縮し、音程が変化します。たとえば、冷房の効いた部屋から外に出るだけで音が下がることもあります。弾く力の強さやピッキングの角度でもズレが生じるほど繊細です。
だからこそ、演奏の前にチューニングを行うことは「楽器の準備」であると同時に、「演奏者としての礼儀」とも言える大切な習慣なのです。
また、チューニングは単なる機械的な作業ではなく、耳を育てる練習の一部でもあります。毎日正しい音を聞いて弦を合わせることで、少しずつ音の違いを感じ取る力が身につき、音感が自然に鍛えられていきます。慣れてくると、チューナーを見なくても「この音は少し高いな」「今のコード、1弦が低いかも」と判断できるようになります。
正しいチューニングを行うことは、ギター上達の土台そのものなのです。
チューニングをしないとどうなる?
もしチューニングをせずに弾いてしまうと、ギター本来の響きが失われてしまいます。
たとえば、コードを押さえても「ジャーン」と鳴らしたときに音が濁り、心地よい響きになりません。音がズレたまま練習を続けると、間違った音を「正しい」と耳が覚えてしまうため、音感の成長を妨げることにもつながります。
録音やアンサンブルでも問題が起きます。自分のギターの音だけズレていて、全体のバランスが崩れてしまうことがあります。特にピアノや他の弦楽器と合わせるときは、わずか数Hzの違いでも明確に「ずれて聞こえる」ため注意が必要です。
また、チューニングが合っていないギターで練習していると、指の押さえ方やリズム感をどれだけ磨いても「合っていない音」のままなので、上達の実感が得られません。これが原因でモチベーションを失う初心者も多いのです。
ギターを弾く前に毎回チューニングを行うことで、正しい音・気持ちの良い響き・安定した演奏を維持でき、結果的に練習効果が格段に上がります。
ギターが音ズレしやすい理由
ギターは構造上、非常に音ズレしやすい楽器です。
まず第一に、弦の張力(テンション)の変化があります。弦は金属でできているため、気温が高いと膨張して緩み、音が低くなります。逆に寒いと収縮して音が高くなります。湿度の変化によっても木材が膨張・収縮し、ネックの角度や弦高が微妙に変わることがあります。これらの要因が重なると、わずか数時間でピッチがズレてしまうのです。
また、新しい弦を張った直後は特に音が安定しません。これは、弦がまだ引っ張られて伸びきっていないためです。新しい弦は何度かチューニングと軽い引っ張りを繰り返すことで、ようやく張力が落ち着きます。さらに、演奏中のピッキングやチョーキング(弦を押し上げる奏法)によってもテンションが変化するため、ギターのチューニングは“弾くたびに変化すると考えるのが基本です。
持ち運びの際の振動や衝撃も音ズレの原因です。ギターケースの中で微妙にペグが動いたり、車内の温度差で弦が緩んだりすることもあります。ライブ前やレッスン前に改めてチューニングを行うプロが多いのはそのためです。
このように、ギターのチューニングは「一度合わせれば終わり」ではなく、「演奏前の準備」として毎回の確認が当たり前です。チューニングを習慣化することで、常にクリアで安定した音を保ち、音楽のクオリティが格段に上がります。
ギターの標準チューニング(レギュラーチューニング)を覚えよう
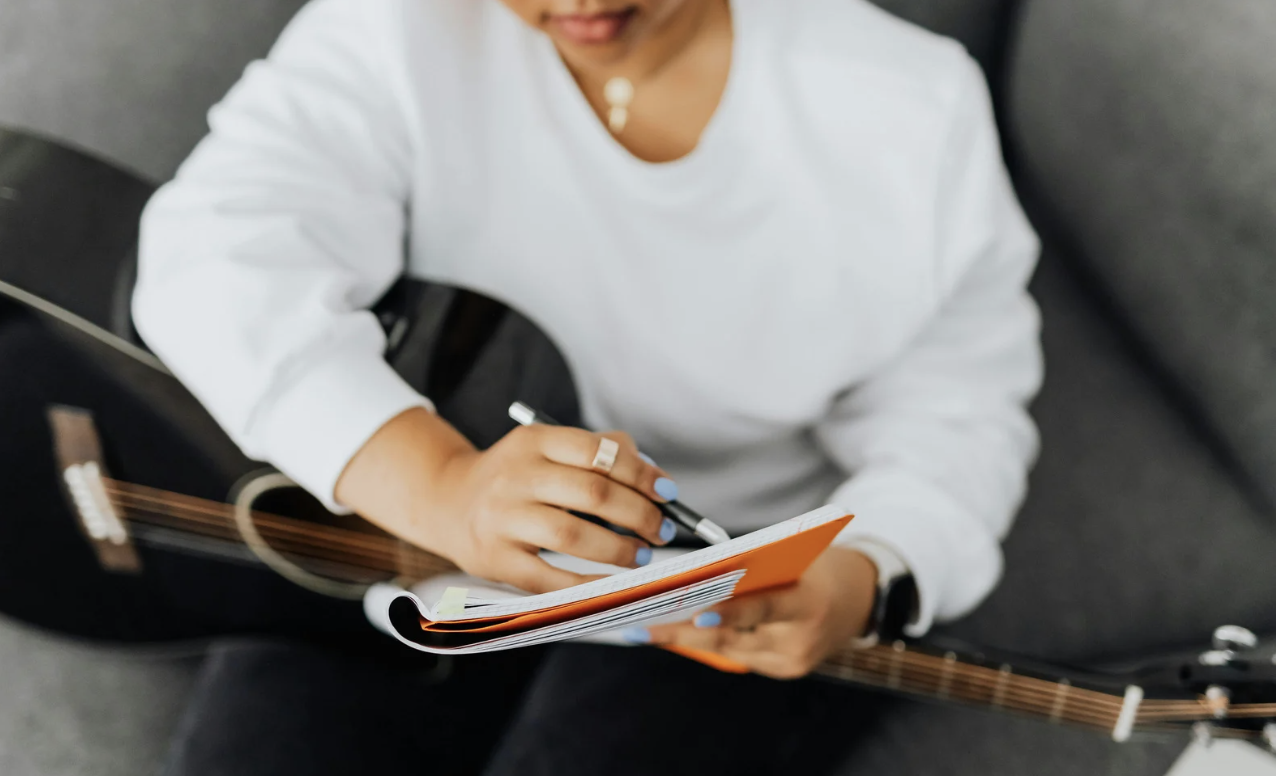
6弦から1弦までの音の並び
ギターの基本となるチューニングは「レギュラーチューニング」と呼ばれ、上から順に
6弦=E、5弦=A、4弦=D、3弦=G、2弦=B、1弦=Eです。この6つの音は「EADGBE」と覚えるのが一般的です。弦の太さによって音の高さが違うため、6弦が一番低く、1弦が最も高い音になります。初心者は、まずこの並びをしっかり覚えることから始めましょう。スマホのチューナーアプリでも、この並びが表示されます。
6弦=E、5弦=A、4弦=D、3弦=G、2弦=B、1弦=E
音名の読み方とドレミ対応表
音名はアルファベットで表記されます。ド=C、レ=D、ミ=E、ファ=F、ソ=G、ラ=A、シ=Bの順です。チューニング中はチューナーにアルファベットが表示されるため、これを理解しておくことが大切です。たとえば6弦なら「E」と表示されたら正しい音という意味になります。初心者の方は最初に「EADGBE」をドレミの感覚に置き換えて覚えると、音楽的な理解が深まり、楽譜を読む力もついていきます。
ド=C、レ=D、ミ=E、ファ=F、ソ=G、ラ=A、シ=B
チューニングの基準音(A=440Hz)とは
チューニングを行う際の基準となるのが「A=440Hz」という数値です。これは世界共通の音の高さの基準で、5弦の開放弦「A(ラ)」が440Hzになるように合わせます。チューナーの設定でこの数値が変更できる場合もありますが、初心者は必ず「440Hz」に固定しておきましょう。バンドで演奏するときなどに他の楽器と音を合わせるためにも、この基準がずれていると全体の音が狂ってしまいます。
チューニングに必要な道具と準備

チューナーの種類と選び方
ギターのチューニングには「クリップ式」「ペダル式」「スマホアプリ」などの方法があります。初心者にはクリップ式チューナーがおすすめです。ヘッドに取り付けて弦の振動を直接拾うため、周囲の音に影響されず正確に合わせられます。スマホアプリも便利ですが、外部の音を拾うため、静かな環境で使うのが理想です。チューナーは練習のたびに使うものなので、操作が簡単で反応の速いモデルを選びましょう。
初心者におすすめのチューナー3選
1つ目はKORGの「Pitchclip 2」。コンパクトでクリップが安定しており、初心者でも扱いやすいモデルです。
2つ目はBOSSの「TU-10」。表示が見やすく、ステージでも使える高性能タイプです。
3つ目は無料アプリ「GuitarTuna」。スマホで手軽にチューニングでき、練習モードも搭載されています。
1つ目はKORGの「Pitchclip 2」
2つ目はBOSSの「TU-10」
3つ目は無料アプリ「GuitarTuna」
どれも精度が高く、ギター初心者のチューニング練習に最適です。最初のうちは使いやすさを優先して選びましょう。
チューニング前に確認すべき3つのこと
チューニングの前に、まず弦とペグの状態を確認しましょう。弦が古く伸びきっている場合、いくら合わせてもすぐズレます。また、ペグが緩んでいると音が安定しません。ギターを弾く前には、軽く弦を指で押さえて伸ばすことで、余分なたるみを取り除きます。さらに、周囲の環境も大切です。冷暖房の風が直接当たる場所や湿気の多い部屋では音が狂いやすくなります。安定した環境で行うのが理想です。
チューニングはセンシティブ!安定した環境で行うことが重要!!
ギターチューニングのやり方(初心者向け手順)
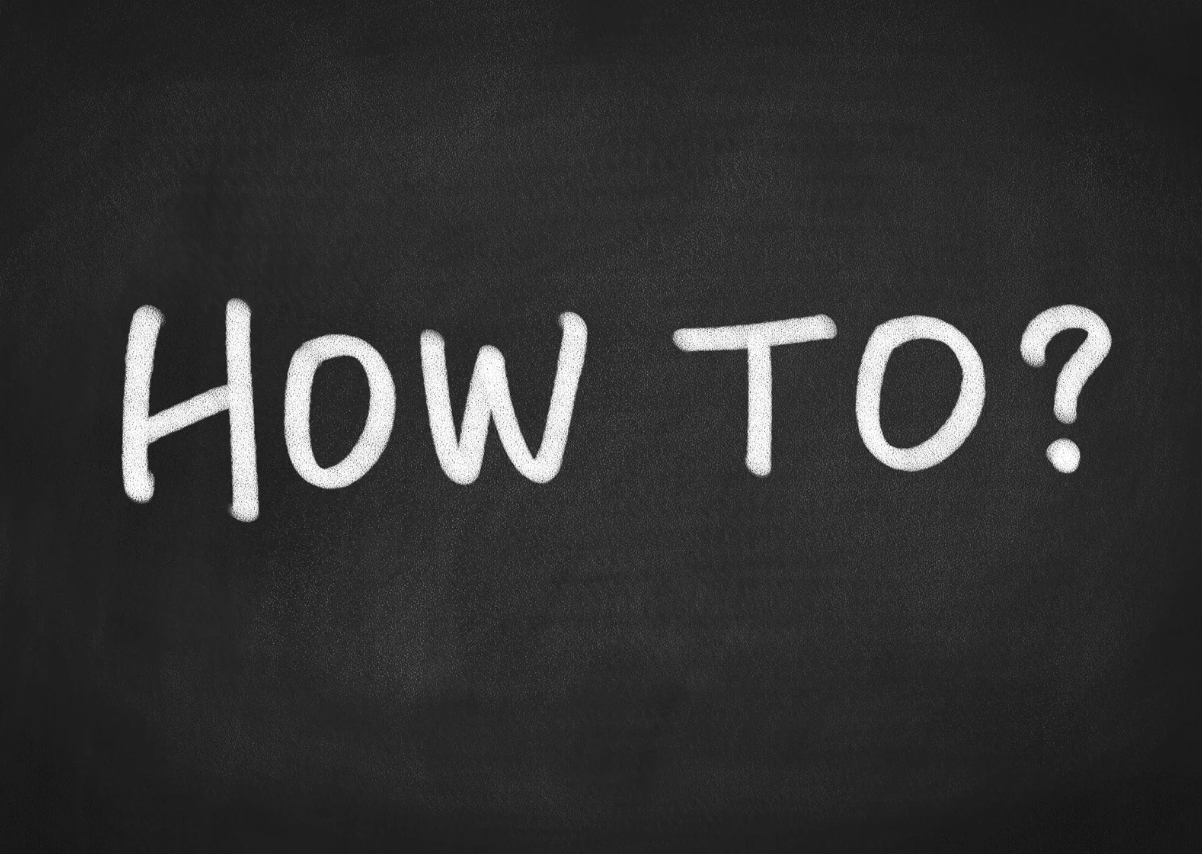
ステップ① チューナーをセットする
チューナーをギターのヘッドに取り付け、電源を入れます。モードが「Guitar」または「440Hz」に設定されているかを確認しましょう。特にクリップ式チューナーの場合、ギターの振動を直接拾うため、静かな環境で行うのがおすすめです。スマホアプリを使う場合は、マイクがしっかり音を拾える位置に置きましょう。チューニングは「音の高さ」を合わせる作業なので、周囲の騒音を避けて集中できる環境を整えることが大切です。
ステップ② 6弦(E)から順に合わせる
最初に6弦(最も太い弦)の音を合わせます。6弦を軽く弾くと、チューナーにアルファベットで「E」と表示されます。針が左に寄っていれば音が低い(フラット)、右に寄っていれば高い(シャープ)状態です。ペグをゆっくり回しながら針が中央に来るように調整します。このとき、音が高すぎた場合は一度少し下げてから再度上げると安定します。6弦は基準音でもあるため、丁寧に合わせることが重要です。
ステップ③ 5弦〜1弦まで順番にチューニング
6弦を合わせたら、次に5弦(A)、4弦(D)、3弦(G)、2弦(B)、1弦(E)の順でチューニングを行います。1弦に向かうほど弦が細く、音が高くなるため、ペグをほんの少し回すだけでも音が変化します。特に2弦と1弦は切れやすいので、力を入れすぎないように注意しましょう。チューナーの針が中央に安定したら、その音が正しいピッチです。1本ずつ確実に合わせることで、全体の響きが美しくなります。
ステップ④ 全体を再確認
全ての弦を合わせたら、もう一度6弦から順にチューニングを確認します。一本の弦を調整すると、他の弦の張力にも影響するため、最初に合わせた弦が微妙にズレてしまうことがあります。再チェックの際は、軽くコード(例:Eメジャー)を弾いてみるのもおすすめです。音が濁らず、各弦がバランスよく響いていればチューニングは完了です。演奏中も気温や弦の伸びでズレることがあるため、こまめな確認が理想です。
ステップ① チューナーをセットする
ステップ② 6弦(E)から順に合わせる
ステップ③ 5弦〜1弦まで順番にチューニング
ステップ④ 全体を再確認
チューニングが安定するコツとよくある失敗
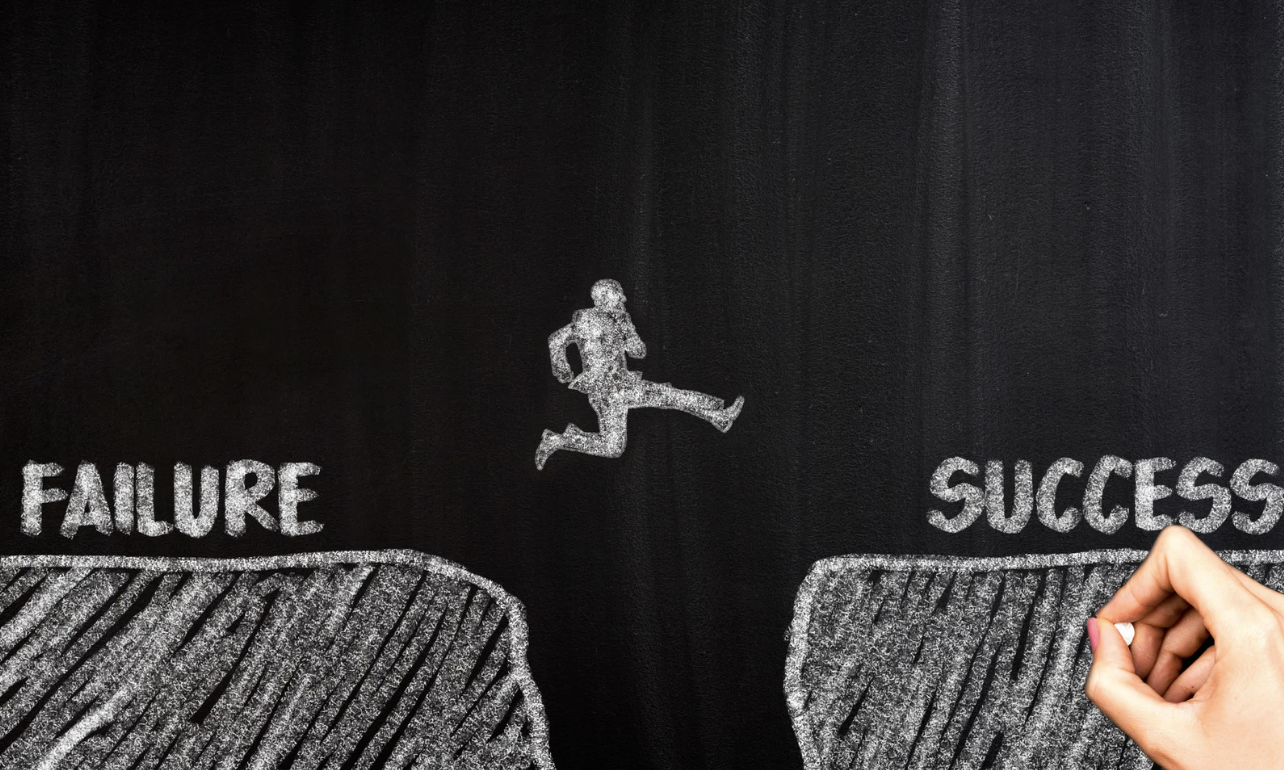
コツ1:ペグは必ず「緩めてから締める」
音が高すぎたとき、いきなりペグを戻して下げると不安定になりやすいため、一度少し下げてから再度ゆっくり上げるのが基本です。こうすることで弦がペグにしっかり巻き付き、演奏中に緩みにくくなります。また、ペグを回す方向はギターの機種によって異なるため、最初に確認しておくと安心です。勢いよく回すと弦が切れることもあるので、ゆっくり慎重に調整しましょう。
コツ2:強く弾きすぎない
チューニング中に弦を強く弾くと、音が不安定になりチューナーが正しく反応しません。軽くピッキングする程度で十分です。特に細い弦ほど、弾く強さで音程が変わりやすいので注意しましょう。チューニングは「優しく」「安定した力」で弦を弾くのがコツです。また、ピックを使う場合は弦に対して直角にあてると、余分なノイズが減り、より正確な結果が得られます。
コツ3:新しい弦は「伸ばして馴染ませる」
弦を張り替えた直後は、まだ伸びきっていないため、すぐに音がズレてしまいます。そのため、張ったあと軽く弦を指で引っ張り、何度かチューニングを繰り返すことが重要です。この作業で弦が安定し、長時間演奏しても音ズレが起きにくくなります。新品の弦は最初の数日間、こまめなチューニングが必要です。慣れてくると、この「弦を馴染ませる感覚」が自然と身につきます。
コツ4:チューナーの設定を間違えない
意外と多いミスが、チューナーの設定間違いです。「ベースモード」や「半音下げモード」になっていると、いくら合わせても正しい音になりません。必ず「Guitar」モードまたは「Standard」モードに設定されているかを確認しましょう。また、基準Hzが「440Hz」以外に設定されていないかもチェックしてください。これを誤ると、他の楽器と合わせたときに音がズレてしまいます。
コツ1:ペグは必ず「緩めてから締める」
コツ2:強く弾きすぎない
コツ3:新しい弦は「伸ばして馴染ませる」
コツ4:チューナーの設定を間違えない
チューナーを使わずに耳で合わせる方法(中級者向け)

5フレットルールでのチューニング
耳チューニングの基本が「5フレットルール」です。6弦の5フレットを押さえると5弦の開放音と同じAの音が鳴るため、この2本を聞き比べながら調整します。同様に、5弦5フレット=4弦開放、4弦5フレット=3弦開放、2弦5フレット=1弦開放という流れで全弦を合わせていきます。ただし、3弦だけは4フレットを使用する点に注意です。耳で音の揺れがなくなったら、2つの弦が正しく合っています。
ハーモニクスを使うチューニング
ハーモニクスとは、弦を軽く触れたまま弾いて倍音を出す方法です。5フレットや7フレットに指を軽く置いて弾くと、美しい倍音が鳴ります。これを利用すると、隣の弦との音の違いがより聴き取りやすくなります。たとえば、6弦5フレットのハーモニクスと5弦7フレットのハーモニクスを比べるなどです。耳チューニングの精度を上げたい人におすすめの練習法で、音感を鍛える効果もあります。
耳チューニングの練習方法
最初はチューナーを併用しながら練習するのがおすすめです。自分の耳で合わせたあと、チューナーで正しいか確認することで、少しずつ音の違いを感じ取れるようになります。慣れてくると、わずかなズレも聞き分けられるようになり、演奏全体の精度が高まります。耳チューニングは難しく感じますが、継続すれば確実に上達します。最終的には、チューナーなしでも自然に正しい音を出せるようになります。
応用編:いろいろなチューニング方法を試そう

半音下げチューニング
半音下げチューニングとは、すべての弦を半音ずつ下げる方法です。たとえば6弦EをE♭に、5弦AをA♭に下げます。音が少し低くなることで、ロックやメタルの重厚なサウンドを出すことができます。また、弦のテンションが緩むため押さえやすくなり、指への負担が減ります。初心者でも簡単に試せる応用チューニングとして人気がありますが、他の楽器と演奏する際は注意が必要です。
ドロップDチューニング
ドロップDチューニングは、6弦だけをEからDに下げる方法です。パワーコードを簡単に押さえられるようになるため、ロックやハードロックでよく使われます。6弦を低く設定することで、低音の響きがより豊かになり、迫力のある演奏が可能です。ドロップDはギター初心者にも挑戦しやすく、同じコードフォームでも違う雰囲気の曲を弾けるようになります。曲に合わせて使い分けましょう。
その他の特殊チューニング
上級者が使う代表的なチューニングとして、オープンG(D-G-D-G-B-D)やDADGAD(D-A-D-G-A-D)があります。これらはコードを押さえなくても美しい響きを作り出すことができ、アコースティックギターやフィンガースタイルの演奏でよく使われます。初心者がいきなり挑戦する必要はありませんが、基本のレギュラーチューニングに慣れてきたら、新しい響きを楽しむために少しずつ試してみると良いでしょう。
よくあるトラブルと対処法

チューナーが反応しない
チューナーが音を拾わないときは、まず電源や電池残量を確認しましょう。特にクリップ式チューナーは電池切れが原因で反応しなくなることが多いです。電源を入れても表示が暗い場合は、早めに電池を交換しましょう。次に、クリップがしっかりギターのヘッド部分に固定されているか確認します。接触が浅いと振動を拾えません。スマホアプリを使う場合は、マイクの許可設定をオンにし、周囲を静かにして弾くと精度が上がります。また、エレキギターの場合はシールドケーブルがしっかり接続されているかも確認してください。
チューニング直後に音がズレる
チューニングが終わった直後に音がズレる場合、弦がまだ安定していない可能性が高いです。新しい弦を張ったときは特に、弦が伸びてテンションが落ち着くまで数回チューニングを繰り返す必要があります。弦を軽く引っ張って伸ばし、再度チューニングを行いましょう。これを数回繰り返すだけで、安定性が格段に上がります。また、ナット(弦が通る溝)部分に摩擦があると弦がスムーズに動かず、ピッチが狂いやすくなります。潤滑剤を少量塗ることで改善される場合もあります。
弦が切れてしまった
弦が切れる主な原因は、過度な締め上げや古い弦の劣化です。チューニングの際は針が中央を超えたら止めるよう意識しましょう。特に1弦と2弦は細く、力を入れすぎると切れやすいので要注意です。また、弦が同じ箇所で何度も切れる場合は、サドルやナットに傷がある可能性があります。その場合は紙やすりで軽く磨くか、楽器店に相談してください。弦は消耗品なので、2〜3か月に一度は交換するのが理想です。新しい弦は音の立ち上がりも良く、チューニングも安定します。
演奏中に音が狂いやすい
演奏中に音がズレる場合は、弾く強さやフォームも見直しましょう。力強くピッキングしすぎると、弦が一時的に伸びて音が高くなります。また、ストラップで立って弾くとギターの角度が変わり、ネックに微妙な力がかかって音がズレることもあります。練習中は座って行い、安定したフォームを身につけることが大切です。ペグの緩みも原因になるため、ドライバーで軽く締めておくと安心です。湿度や温度によっても変化するため、保管環境にも気を配りましょう。
チューニングが合っているのにコードが濁る
チューナーで合わせても、コードを弾いたときに「濁って聞こえる」と感じることがあります。これは、押さえ方や指の力加減によるピッチのズレが原因です。弦を強く押さえすぎると音が高くなり、特に初心者はこの傾向が強いです。軽く押さえても音が出る位置を探し、必要以上に力を入れないよう意識しましょう。また、弦高が高すぎるギターも音程が狂いやすいため、気になる場合はリペアショップで調整を依頼すると良いでしょう。
チューニングを習慣化するコツ

練習前に必ずチューニングする
ギターの練習を始める前には、必ずチューニングを行いましょう。毎回確認することで、弦の状態や音の変化に敏感になり、自然と音感が育ちます。最初のうちは「ズレているかも?」と感じたらすぐにチューナーで確かめることが大切です。慣れてくると、チューナーを見る前に違和感を感じ取れるようになります。正しい音で練習を積み重ねることが、確実な上達への第一歩です。プロの演奏家も毎回欠かさずチューニングしています。
1日1回の「音合わせ習慣」
忙しい日でも1日1回はギターを手に取り、音を合わせてみましょう。たとえ5分でも、チューニングを行うことで楽器への愛着が深まり、練習を継続しやすくなります。チューニングは単なる準備ではなく、楽器と対話する時間でもあります。「今日は少し音が低いな」「この弦の響きが違うな」と感じることで、自分の耳とギターのコンディションの変化を意識できるようになります。こうした日々の積み重ねが、確実な上達につながるのです。
音感トレーニングにもなる
チューニングは音感を鍛える最良のトレーニングです。チューナーの針が中央から少しズレたときの音の違いを意識して聴くことで、わずかなピッチの変化を感じ取る力がつきます。最初はチューナーの表示を見ながら確認し、徐々に自分の耳だけで判断する練習を取り入れてみましょう。上達してくると、曲の中で自然にピッチを補正できるようになります。耳でチューニングできるようになることは、演奏者としての大きな成長です。
長持ちさせるメンテナンス習慣
チューニングの精度を保つためには、ギター自体のメンテナンスも欠かせません。弾き終わった後は、弦を軽く緩めてテンションを和らげましょう。ネックへの負担を減らし、長期間安定した音を保てます。また、湿度管理も重要です。乾燥するとネックが反りやすく、音程が不安定になります。ケース内に湿度調整剤を入れると効果的です。ギターを丁寧に扱うことで、チューニングも安定し、より良い音を長く楽しめます。
まとめ:チューニングをマスターすればギターがもっと上達する

ギターチューニングは、初心者が最初に身につけるべき最重要スキルです。最初は手間に感じても、正しいやり方を理解すれば5分で完了します。チューナーを使って丁寧に6弦から順番に合わせることを習慣にし、弦の状態や気温による変化を観察しましょう。チューニングを怠ると、どんなに練習しても正しい音が出せず、上達が遅れてしまいます。逆に、音が合っているだけで演奏が気持ちよくなり、練習のモチベーションも上がります。
「音が合っている」という安心感は、自信と上達の第一歩。チューニングを通して音を聴く力を磨き、ギターとの一体感を感じながら、音楽をもっと楽しみましょう。
アサヒ音楽教室の体験レッスンで、正しいチューニングを体感しよう

ギターチューニングを実践的に学びたい方には、アサヒ音楽教室の体験レッスンがおすすめです。講師がマンツーマンで、チューナーの使い方から弦交換後の安定したチューニング方法、耳で合わせる練習まで丁寧に指導します。初心者でも安心できる環境で、正しい音を聴き分ける力を育てられます。実際の演奏を通して音の違いを体感できるため、自宅練習の質も格段に向上します。
体験レッスンのお申し込みは、アサヒ音楽教室の公式サイトからいつでも受付中です。あなたのギターライフを、正しいチューニングから始めましょう。
関連記事
-

2026年2月16日
講師ブログピアノ教室の体験レッスンは何を見る?後悔しないためのチェックポイントと失敗しない先生の選び方完全ガイド
ピアノ教室の体験レッスンへ行く前に知っておきたい基礎知識 ピアノ教室選びで「体験」が最も重要視される理由 ピアノという楽器は、他の習い事と比較しても講師と生徒が一対一で向き合う時間が非常に長いのが特徴...
-

2026年2月16日
講師ブログ楽器演奏は最高の「脳の筋トレ」!ストレス解消から認知症予防まで驚きの効果を徹底解説
音楽を趣味にするメリットとは?人生の質(QOL)が劇的に変わる理由 日々の仕事や家事に追われ、ふと「自分を豊かにする時間が足りない」と感じることはありませんか。ストレス社会と呼ばれる現代において、心の...
-

2026年2月16日
講師ブログ音楽教室の振替は無料が安心!後悔しない選び方と回数・期限・注意点を徹底解説【2026年最新ガイド】
急な予定変更や体調不良…月謝を無駄にしたくない方へ 音楽教室に通い始める際、多くの方が抱く不安の一つが「急な予定が入ったときにレッスンはどうなるのか」という点です。仕事での残業や急な出張、あるいは自分...
Blog 講師ブログ
-
2026年2月16日
音楽教室の振替は無料が安心!後悔しない選び方と回数・期限・注意点を徹底解説【2026年最新ガイド】
急な予定変更や体調不良…月謝を無駄にしたくない方へ 音楽教室に通い始める際、多くの方が抱く不安の一つが「急な予定が入ったときにレッスンはどうなるのか」という点です。仕事での残業や急な出張、あるい...
-
2026年2月16日
ピアノ教室の体験レッスンは何を見る?後悔しないためのチェックポイントと失敗しない先生の選び方完全ガイド
ピアノ教室の体験レッスンへ行く前に知っておきたい基礎知識 ピアノ教室選びで「体験」が最も重要視される理由 ピアノという楽器は、他の習い事と比較しても講師と生徒が一対一で向き...
-
2026年2月16日
楽器演奏は最高の「脳の筋トレ」!ストレス解消から認知症予防まで驚きの効果を徹底解説
音楽を趣味にするメリットとは?人生の質(QOL)が劇的に変わる理由 日々の仕事や家事に追われ、ふと「自分を豊かにする時間が足りない」と感じることはありませんか。ストレス社会と呼ばれる現代...
Course コース一覧
Area スタジオエリア一覧
| 東京23区 |
|---|
| 東京23区外 |
|---|
| 神奈川県 |
|---|
| 千葉県 |
|---|
| 埼玉県 |
|---|


