Blog 講師ブログ
2025年10月27日
ピアノのペダルの意味と使い方を徹底解説|初心者〜上級者

ピアノペダルとは?その「意味」を整理する
ペダルの語源・歴史的背景
ピアノのペダルは、楽器の歴史とともに進化してきた装置です。もともと「ペダル」という言葉は、ラテン語の「pes(足)」に由来しており、「足で操作するもの」という意味を持っています。18世紀のフォルテピアノには、現在のようなペダルではなく、膝で操作するレバーが付いていました。その後、より自然に使えるよう足元に移され、現在の三本ペダルの形が確立しました。ペダルは単なる補助装置ではなく、音の響きや表現をコントロールするために欠かせない要素です。
ペダル=“足による制御装置”の基本構造

ピアノのペダルは、鍵盤を弾いた後の音の響きを足でコントロールするための装置です。内部には棒やレバーがつながっており、踏むことでハンマーやダンパーなどが動きます。ペダルを使うことで、弦の振動を延ばしたり、音色を柔らかくしたりすることが可能です。演奏者の手は音を生み出し、足はその音の余韻や質感を操る——まさに「もう一つの表現手段」です。特に右ペダルは、初心者でも最初に体験するペダル操作として知られています。
なぜペダルが生まれたか?目的と役割
ピアノのペダルは、より豊かな響きを生み出すために考案されました。初期のピアノでは音がすぐに消えてしまい、歌うような演奏が難しかったのです。ペダルを踏むことで弦の振動が持続し、音が空間全体に広がります。また、音と音のつながりを滑らかにし、まるで人の声のように「歌う」表現を可能にします。さらに、ペダルを使い分けることで曲の雰囲気や感情を繊細に描けるようになります。まさにペダルは、ピアノの“心”を映す大切なパーツです。
ペダルを使うことで得られる演奏上のメリット
ペダルを使うと、音楽に深みと立体感が生まれます。たとえば右ペダルを踏むと音が共鳴し、和音全体が一つに溶け合うような響きになります。左ペダルでは音量を抑え、柔らかく穏やかな表情を作り出せます。中央ペダルを使えば、特定の音だけを響かせるという高度なコントロールも可能です。これらを適切に使い分けることで、同じ曲でも全く違う印象を与えられます。ペダルは単なる「足の動作」ではなく、「音楽の表現力そのもの」と言えるでしょう。
代表的なペダル3本の意味と役割(グランドピアノの場合)

右ペダル:ダンパーペダル(サスティンペダル)の意味・機能
ピアノの右ペダルは「ダンパーペダル」または「サスティンペダル」と呼ばれ、最も頻繁に使われるペダルです。踏むと、弦に触れていたダンパーがすべて持ち上がり、音が止まらずに響き続けます。これにより、手を離しても音が伸び、音楽に豊かな余韻が生まれます。例えば、和音を弾いた後に右ペダルを踏むと、各音が共鳴し合い、美しいハーモニーが広がります。クラシックからポップスまで、あらゆるジャンルの演奏で欠かせない存在です。
左ペダル:ソフトペダル(ウナ・コルダ/シフトペダル)の意味・機能
左ペダルは「ソフトペダル」または「ウナ・コルダ」と呼ばれ、音を柔らかく、静かにするためのものです。グランドピアノでは、ペダルを踏むとハンマー全体が少し横にずれ、叩く弦の数が三本から二本、あるいは一本になります。その結果、音の強さが弱まり、繊細で内省的な響きが得られます。ショパンやドビュッシーのように、静けさや夢幻的な雰囲気を表現する曲では欠かせません。ペダルを踏む力加減一つで、音の質感が変わる点も魅力です。
中央ペダル:ソステヌートペダル(およびアップライトでの例)の意味・機能
中央ペダルは「ソステヌートペダル」と呼ばれ、特定の音だけを保持する機能を持ちます。グランドピアノでは、音を出した直後にこのペダルを踏むと、その音だけが響き続け、他の音は影響を受けません。複雑な和音や、片手で保持しきれない音を残したいときに便利です。一方、アップライトピアノでは「マフラーペダル」として弱音機能を果たす場合が多く、フェルトが弦にかかって全体の音量を下げます。夜間練習などに役立つ実用的なペダルです。
グランドピアノ vs アップライトピアノのペダル事情

機構の違い:グランドとアップライトで変わるペダルの働き
グランドピアノとアップライトピアノでは、ペダルの構造と機能が微妙に異なります。グランドでは弦が水平に張られているため、ペダルを踏むと直線的にダンパーが上がりますが、アップライトは縦型構造なので、ワイヤーやレバーを介して伝達されます。そのため反応の速さや踏み心地が異なり、繊細なペダリングはグランドの方が表現しやすいといわれます。ただし、アップライトでも十分に練習可能で、家庭用として高い性能を持つモデルも増えています。
ペダル本数・構成の違い(2本型・3本型)

一般的に、グランドピアノは三本のペダルが標準ですが、アップライトピアノには二本しかないタイプも存在します。特に古いモデルやコンパクトタイプでは、中央ペダルが省略されていることがあります。最近では家庭用モデルでも三本ペダル仕様が主流となっており、弱音ペダル(マフラーペダル)が中央に搭載されています。三本あるとより多彩な表現が可能になり、レッスンや発表会でもグランドと同じ感覚で練習できる点が魅力です。
楽譜上のペダル記号・表記と読み方

右ペダルを表す記号:「Ped.」「*」「—」など
楽譜の中で右ペダルを使う箇所には、「Ped.」という文字や、「—」「*」といった記号が記されます。「Ped.」はペダルを踏む位置を、「*」は離す位置を示すものです。また、長い横線が続く場合は、その間ペダルを踏み続けるという意味になります。作曲家によっては細かく指定せず、演奏者の感覚に委ねている場合も多いです。そのため、ただ記号を機械的に追うのではなく、実際の響きを聴きながら調整することが大切です。
左ペダルを表す記号:「una corda(u.c.)」「tre corda(t.c.)」など
左ペダルは、主に「una corda(ウナ・コルダ)」と表記されます。これは「1本の弦で」という意味で、ペダルを踏むことで音が柔らかくなることを示しています。反対に「tre corda(トレ・コルダ)」と書かれている場合は、ペダルを離して元の位置に戻す指示です。クラシックの楽譜では頻繁に見られ、特にロマン派の作曲家たちは、音の表情を繊細にコントロールするためにこの記号を多用しました。ペダル記号を理解することで、作曲家の意図がより明確に伝わります。
中央ペダル・その指定の記号・少ないが使われるケース
中央ペダルを示す記号はあまり一般的ではありませんが、「Sost. Ped.」や「Sost.」と書かれている場合があります。これはソステヌートペダルの略で、「一部の音だけを保持する」という意味です。使用例は限られますが、近代以降の楽曲や、現代曲の中では特定の音を長く響かせたいときに指定されることがあります。アップライトピアノの場合は構造上この機能がないため、実際の演奏時には右ペダルで代用するなど、状況に応じて工夫が必要です。
指示がない場合の判断基準・自分で決めるポイント
多くの楽譜では、ペダルの記号が細かく書かれていないことがあります。これは演奏者の判断に任されているケースで、耳を使って自分で最適な響きを探すことが求められます。例えば、和音が濁らないように短めに踏む、旋律が流れるように響かせたいときは長めに保つなど、曲のテンポやホールの響きに合わせて調整しましょう。ペダルの踏み方一つで音楽の印象が変わるため、自分なりの「ペダリング感覚」を育てることが大切です。
具体的な楽譜例(初心者~中級者向け)と読み取り方
たとえばベートーヴェンの「エリーゼのために」では、右ペダルを使ってメロディーの余韻を残しながら、左手の伴奏を自然につなげる効果があります。一方、ドビュッシーの作品では、ペダルが“音の霧”を作るような役割を果たします。こうした曲では、記号の有無よりも、実際に響きを聴き分けて踏み替える感覚が重要です。初心者のうちは、指導者の助言を受けながら、どのタイミングで踏み、どのくらいの深さで踏むのかを身体で覚えていきましょう。
ペダルの使い方・タイミング・テクニック

正しい姿勢・足の置き方(かかとを地面に付ける等)
ペダルを美しく操作するためには、正しい姿勢が欠かせません。椅子の高さは、かかとがしっかり床につき、つま先で自然にペダルを踏める位置に調整します。かかとを浮かせてしまうと安定性を失い、繊細なペダリングが難しくなります。特に右足は常にペダルの上に軽く添えるようにし、踏み込むときに無理な力を入れないよう心がけましょう。力まず、体全体のバランスの中で足を使うことが、滑らかなペダル操作の基本です。
タイミングの基本:音を出した直後・次の音に移る直前に踏む・離す
ペダルを踏むタイミングは、音の流れを滑らかにするための要です。基本的には「音を出した直後に踏み、次の音を弾く直前に離す」という動作を意識します。これを「後踏み」と呼びます。この踏み替えが遅すぎると音が濁り、早すぎると響きが途切れてしまいます。慣れないうちは、手と足の動作を分けてゆっくり練習すると良いでしょう。テンポの速い曲では、足のリズムを体で覚えるように反復するこ/とが上達の近道です。
ハーフペダル・後踏み・前踏みなど応用テクニック
演奏表現が上達すると、ペダルを「全踏み」ではなく「半踏み」することで、響きの量をコントロールできるようになります。これをハーフペダルと呼びます。完全に踏むと音が濁る場合、半分だけ踏み込むことで響きを保ちながら透明感を維持できます。また、音を出す前に踏む「前踏み」や、音を出してから踏む「後踏み」など、音楽のニュアンスによって使い分けます。これらのテクニックを身につけることで、より感情豊かな演奏が可能になります。
踏みすぎ・離しすぎのリスク(音が濁る・響きがぼやける)
初心者によく見られる失敗が、「踏みっぱなし」にしてしまうことです。常に右ペダルを踏み続けると、音が重なりすぎて濁った響きになります。反対に、踏む時間が短すぎると、音が途切れて乾いた印象になってしまいます。演奏中は、耳で響きを聴きながら微調整する意識を持ちましょう。曲のテンポや音域、使用する和音によっても最適なペダル量は変わります。ペダルを“踏む”というより“呼吸する”ように扱うと、自然で美しい響きになります。
初心者向け練習法:ペダルなし→ありで聴き比べる
ペダルの効果を体感するには、まずペダルを使わずに曲を弾いてみましょう。その後、同じ曲をペダルありで演奏してみると、響きの違いがはっきりと分かります。この「聴き比べ練習」は、耳を鍛えるのに最適です。さらに、ペダルを踏む深さを変えてみることで、音の伸び方や明るさの変化も感じ取れるようになります。日々の練習で意識的に行うと、自分の音への感覚が磨かれ、自然にペダル操作が上達します。
上級者向け:ペダルを表現手段として使う(ニュアンス・余韻・音色の変化)
上級者になると、ペダルは単なる響きの延長装置ではなく、音色そのものを変化させる表現手段として扱われます。曲の中で感情の起伏を描くとき、強く踏むか浅く踏むかによって印象が大きく変わります。特にロマン派以降の作品では、ペダル操作が作曲家の意図の一部とされています。たとえばショパンやラヴェルの曲では、ペダルの踏み替えによって音が滲むように響く瞬間があり、それが音楽の詩的美しさを生み出します。
よくあるペダルの疑問・悩みとその解決策

「踏んだら響きが濁る」「なんか踏み怪しい音になる」
音が濁る原因の多くは、ペダルの踏み替えが遅れていることです。ペダルを長く踏みすぎると、前の音が残りすぎて新しい音と混ざってしまいます。解決策として、「弾く→すぐ踏む→すぐ離す」というリズムを意識して練習しましょう。音が澄んで響く位置を探すことが重要です。
「いつ離せばいいか分からない」
ペダルを離すタイミングは、響きをどのように処理したいかによって異なります。基本的には「次の和音を弾く直前」に離すことで、自然なつながりを保つことができます。慣れないうちは、ゆっくりテンポで「弾く→踏む→離す」の順番を意識して練習しましょう。足を急に離すと音が途切れるため、少しずつ戻すようにして音の流れを滑らかに保つことが大切です。耳で響きを感じ取りながら、呼吸をするようにペダルを扱うことが理想です。
「楽譜にペダル記号がない…どうすれば?」
多くの曲ではペダル記号が書かれていません。これは、演奏者の感性でコントロールする余地を残しているためです。ペダルの使用は、楽器の種類、ホールの響き、演奏テンポによっても最適解が変わります。まずはメロディを歌うように弾き、その響きに必要なだけペダルを足すようにしましょう。ペダルは「踏むもの」ではなく「聴いて調整するもの」。自分の耳が最も信頼できるガイドとなります。録音して聴き返すのも効果的な方法です。
「電子ピアノでペダル効果が感じにくい」
電子ピアノのペダルは、構造上アコースティックピアノとは異なり、響きの広がりを物理的に再現することが難しい場合があります。そのため、思ったよりも音の変化が少なく感じることがあります。対策としては、ハーフペダル対応機種を選ぶこと、またはヘッドホンではなくスピーカーで音を聴くことです。近年のデジタルピアノは共鳴シミュレーション機能が進化しており、ペダル効果の再現度も高まっています。練習環境に合わせて設定を調整してみましょう。
「子ども・足が届かない/ペダルが効かない感じがする」
小さな子どもがペダルを使う場合、足が届かず正しく踏めないことがあります。その際は「補助ペダル」や「足台」を使用するのが効果的です。これにより、自然な姿勢を保ちながらペダル操作を学べます。また、ペダルが重いと感じる場合は、ピアノのメンテナンス不足も考えられます。内部の金属棒やバネが固くなっていることもあるため、定期的に調整を依頼しましょう。正しい姿勢と環境が、上達への第一歩です。
「夜に練習したいけど音がうるさい」
マンションなどの集合住宅では、夜間のペダル使用が難しいことがあります。アップライトピアノには多くの場合「マフラーペダル(弱音ペダル)」があり、これを踏むとフェルトが弦にかかり、音量が大幅に下がります。また、電子ピアノの場合はヘッドホンを利用することで時間を選ばず練習可能です。夜でも音楽を楽しみたい方は、マフラーペダル付きのモデルやサイレント機能搭載ピアノを選ぶとよいでしょう。
ケーススタディ:ペダルを使った演奏改善の実例
初心者の子どもがペダルを使い始めて音が変わった話

ペダルを使い始めたばかりの小学生の生徒がいました。最初は踏みっぱなしで音が濁ってしまいましたが、先生と一緒に「踏む→離す→聴く」を繰り返すうちに、徐々に音の違いを感じ取れるようになりました。最初に覚えたのは、和音を弾いたあとに軽くペダルを踏んで余韻を作る方法。これだけで演奏の印象が大きく変わり、本人も「自分の音がきれいになった」と感じたそうです。ペダルは音の世界を広げる魔法のような道具です。
中級者がペダルを効果的に使いこなせるようになった例
ある大人の生徒は、曲全体の響きを「濁って聞こえる」と悩んでいました。録音して聴いてみると、ペダルを離すタイミングが遅れていることが原因でした。そこで、指とペダルの動作を分けて練習し、「踏み替えの瞬間」に集中。2週間ほどで響きが劇的に変化し、透明感が増しました。ペダルは感覚的な要素が強いですが、録音や映像を通して客観的に見ることで、課題が明確になります。
先生・レッスン時の指導ポイント
レッスンでは、手の動きに加えて足の動作も丁寧に指導されます。特に子どもや初心者の場合、最初から複雑なテクニックを教えるのではなく、「音を聴いて踏む」ことに重点を置きます。ペダルを早く覚えようとすると、指のタッチが軽くなり、音が薄くなりがちです。先生は「まず手で美しい音を出す→その音を足で支える」という順番を大切にします。ペダル操作は、手の音を活かすためのサポートなのです。
録音・動画撮影時に「足元のペダル」が映っていない
発表会やコンクールで録音するとき、映像に足元が映っていないケースがあります。これはペダル操作を客観的に確認する機会を逃すことにもつながります。スマートフォンを少し低い位置に設置して、ペダルの動きを撮影してみましょう。音の響きと足のタイミングを比較することで、自分の癖や遅れが視覚的にわかります。上達への近道は「耳」と「目」での確認です。
選び方・メンテナンス・練習環境づくり
ペダル付きの電子ピアノ・補助ペダルの選び方
電子ピアノを購入する際は、必ず「3本ペダル対応」または「ハーフペダル対応」の機種を選びましょう。安価なモデルではペダルが1本しかなく、細かい表現が難しくなります。特にクラシック曲を演奏したい場合は、ペダルの踏み込み具合が反映されるタイプが理想です。また、小さな子どもには身長に合わせた補助ペダルを用意し、足の形を自然に保てるようにすることが上達につながります。
ピアノ本体のペダルのメンテナンス(動きが重い/ガタつく)
ペダルの反応が鈍い、踏むと異音がする、といった症状がある場合は、内部の部品が摩耗している可能性があります。定期的に調律師に点検を依頼し、ペダルの動きや音をチェックしましょう。ネジの緩みやホコリの蓄積も原因となることがあります。ペダルのコンディションが悪いと、演奏の表現力にも影響します。長く美しい音を保つためには、年に一度のメンテナンスがおすすめです。
ペダル練習専用時間を設けるメリット
多くの人は、曲練習の中で自然にペダルを使いますが、あえて「ペダルだけ」を意識する時間を作ることも有効です。例えば、同じ和音を弾きながらペダルの深さやタイミングを変えて響きを比べる練習です。これにより、耳の感度が高まり、細かいコントロールができるようになります。ペダル練習は単調に感じるかもしれませんが、最終的に演奏全体の完成度を大きく高める重要な訓練です。
練習環境(カーペット・ペダルマット・防振・夜間配慮)
自宅で練習する際、ペダルを踏む音が床に伝わることがあります。特にマンションでは、防音マットや防振ペダルボードを設置することで、騒音を軽減できます。カーペットの厚さや椅子の高さも、踏みやすさに影響します。快適な環境を整えることが、集中力の維持や上達スピードに直結します。練習スペースを整えることもまた、音楽を楽しむための大切な準備の一つです。
まとめ/次のステップ

ペダル理解が演奏に与える影響の振り返り
ペダルを正しく理解することで、音楽の世界は一気に広がります。響きの持続、音色の変化、感情の表現——これらすべてを支えるのがペダルの役割です。初心者はまず右ペダルの基本的な踏み替えから始め、少しずつ感覚を身につけていきましょう。正しい知識と練習の積み重ねが、美しい音を作る鍵となります。
今日から取り組める“ペダル使いの一歩”
すぐにできる練習法として、「短いフレーズを弾きながらペダルの有無を聴き比べる」ことをおすすめします。自分の耳で違いを感じることが、理解を深める最良の方法です。最初は難しくても、継続すれば自然に足と耳が連動してきます。ペダルは“体で覚える技術”です。
振り返りチェックリスト(「何を踏むか」「いつ踏むか」「どう変わるか」)
1. 音を出した後に踏んでいるか
2.響きを耳で確認しているか
3.音が濁っていないか
4.ペダルを離すタイミングが早すぎないか
5.曲の雰囲気に合った踏み方をしているか
この5点を意識するだけで、ペダルの精度が大きく向上します。
おすすめ参考書・動画・レッスンの案内
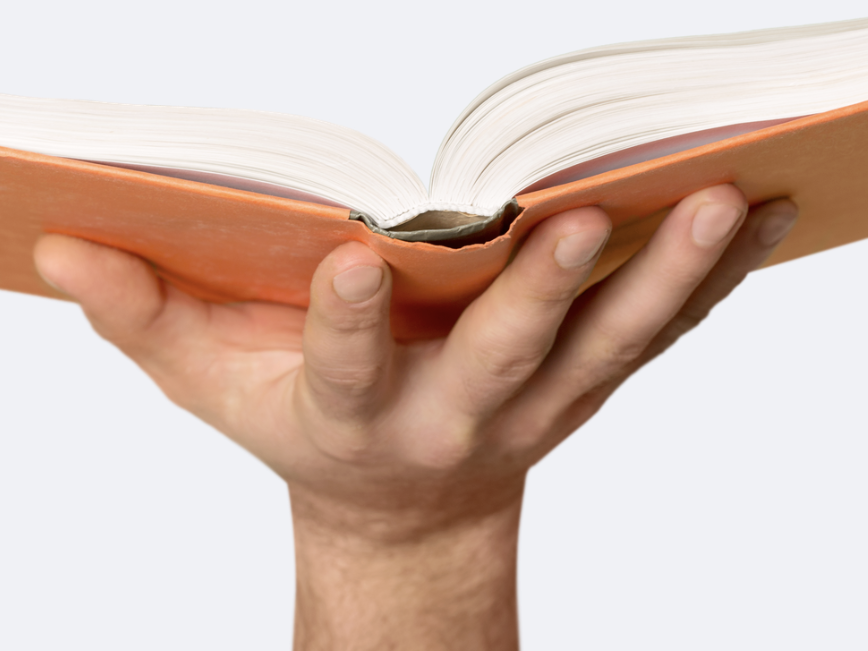
ペダル技術を深めたい方には、専門書「ピアノペダル完全攻略」や、YouTubeのレッスンチャンネル「Classy Piano Study」などがおすすめです。また、音楽教室でプロの講師に直接アドバイスを受けることで、より短期間で上達できます。学びを継続し、自分だけの“理想の響き”を見つけていきましょう。
関連記事
-

2026年2月16日
講師ブログピアノ教室の体験レッスンは何を見る?後悔しないためのチェックポイントと失敗しない先生の選び方完全ガイド
ピアノ教室の体験レッスンへ行く前に知っておきたい基礎知識 ピアノ教室選びで「体験」が最も重要視される理由 ピアノという楽器は、他の習い事と比較しても講師と生徒が一対一で向き合う時間が非常に長いのが特徴...
-

2026年2月16日
講師ブログ楽器演奏は最高の「脳の筋トレ」!ストレス解消から認知症予防まで驚きの効果を徹底解説
音楽を趣味にするメリットとは?人生の質(QOL)が劇的に変わる理由 日々の仕事や家事に追われ、ふと「自分を豊かにする時間が足りない」と感じることはありませんか。ストレス社会と呼ばれる現代において、心の...
-

2026年2月16日
講師ブログ音楽教室の振替は無料が安心!後悔しない選び方と回数・期限・注意点を徹底解説【2026年最新ガイド】
急な予定変更や体調不良…月謝を無駄にしたくない方へ 音楽教室に通い始める際、多くの方が抱く不安の一つが「急な予定が入ったときにレッスンはどうなるのか」という点です。仕事での残業や急な出張、あるいは自分...
Blog 講師ブログ
-
2026年2月16日
音楽教室の振替は無料が安心!後悔しない選び方と回数・期限・注意点を徹底解説【2026年最新ガイド】
急な予定変更や体調不良…月謝を無駄にしたくない方へ 音楽教室に通い始める際、多くの方が抱く不安の一つが「急な予定が入ったときにレッスンはどうなるのか」という点です。仕事での残業や急な出張、あるい...
-
2026年2月16日
ピアノ教室の体験レッスンは何を見る?後悔しないためのチェックポイントと失敗しない先生の選び方完全ガイド
ピアノ教室の体験レッスンへ行く前に知っておきたい基礎知識 ピアノ教室選びで「体験」が最も重要視される理由 ピアノという楽器は、他の習い事と比較しても講師と生徒が一対一で向き...
-
2026年2月16日
楽器演奏は最高の「脳の筋トレ」!ストレス解消から認知症予防まで驚きの効果を徹底解説
音楽を趣味にするメリットとは?人生の質(QOL)が劇的に変わる理由 日々の仕事や家事に追われ、ふと「自分を豊かにする時間が足りない」と感じることはありませんか。ストレス社会と呼ばれる現代...
Course コース一覧
Area スタジオエリア一覧
| 東京23区 |
|---|
| 東京23区外 |
|---|
| 神奈川県 |
|---|
| 千葉県 |
|---|
| 埼玉県 |
|---|


