Blog 講師ブログ
2025年10月28日
ギターピック完全ガイド|選び方・種類・おすすめモデル・正しい使い方を徹底解説

ギターピックに迷う人へ
ギターを始めたばかりの方や、長く弾いているのに「しっくりくるピックが見つからない」と感じている方は多いのではないでしょうか。ピックは小さなアイテムですが、音の質・弾きやすさ・リズム感に直結する重要な要素です。本記事では、ギターピックの選び方、形や素材・厚さの違い、初心者におすすめのモデル、正しい持ち方や使い方までを丁寧に解説します。ピック選びに迷うすべての人が、この記事で「これだ」と思える一本を見つけられるはずです。
ギターピックの基礎知識

ピックとは?ギター演奏に欠かせない理由
ギターピックとは、弦を弾くために使う小さな三角形の道具で、ギターの音を直接生み出す「指先の延長」のような存在です。ピックを使うことで、音量・アタック・表現力を自在にコントロールできます。特にエレキギターやアコースティックギターでは、ピックの種類によってサウンドの印象が大きく変わります。自分に合ったピックを選ぶことは、演奏の快適さと音質を高める第一歩と言えるでしょう。
ピックが演奏・音質に与える影響
ピックの素材や厚さ、形状によって、ギターの音は劇的に変化します。たとえば薄いピックは軽快で柔らかなストローク音を生み、厚いピックは力強いアタックと音の深みを生みます。素材によっても違いがあり、セルロイドは滑らかで自然な音、トーテックスはグリップが良く歯切れのいいサウンドを出せます。ピックは“音のキャラクター”を作る重要なパーツなのです。
初心者が感じやすいピックの悩み
初心者が最初に直面する悩みの多くは、「ピックが滑る」「音がこもる」「弾きにくい」というものです。これらは、ピックの厚さや形、素材が自分に合っていないことが原因です。また、正しい持ち方を知らないまま練習を続けると、力が入りすぎて弦を強く弾きすぎる傾向もあります。まずは、初心者向けの標準的な形と厚さを選び、フォームを整えることから始めましょう。
ギターピックの選び方【形状・素材・厚さが重要】

形状で選ぶ — 音色と弾きやすさを左右する要素
ピックの形状には、ティアドロップ型、トライアングル型、ジャズ型などがあります。形状によってピッキングの角度や弦への当たり方が変わるため、自分の演奏スタイルに合う形を選びましょう。
| ティアドロップ型 | 最も標準的で、初心者にも扱いやすい形 |
| トライアングル型 | 持ちやすく安定感がありストローク向き |
| ジャズ型 | 小型で先端が尖っており速弾きや細かいリード演奏に最適 |
素材で選ぶ — 音質とグリップ感の違い
ピックの素材は音のキャラクターに大きく影響します。アクリル製や金属製のピックもあり、独特の明瞭なサウンドを作れます。
| セルロイド | 滑らかで温かみのある音を生み最もオーソドックス |
| ナイロン | 柔軟性があり軽やかなストローク向き |
| トーテックス(デルリン) | 耐久性が高く、滑りにくいので安定感がある |
| ウルテム | 硬質で明るいトーンを出すためリードギターに人気 |
厚さ(ゲージ)で選ぶ — 音の強さと弾き心地を調整
ピックの厚さは0.5mm~1.5mm程度の範囲で分かれており、演奏スタイルに応じて選ぶことが重要です。薄いピック(0.5mm前後)は柔らかく、ストローク時の音が明るく軽快になります。中厚(0.7〜0.9mm)は汎用性が高く、ストロークとリード両方に使いやすい厚さです。厚いピック(1.0mm以上)は硬く、音の輪郭がはっきりと出るためリードプレイに向いています。
演奏スタイル別のおすすめ厚さ
演奏スタイルによって理想のピックの厚さは異なります。アコースティックギターで弾き語り中心なら、薄め(0.6mm前後)が自然な音の揺れを表現しやすいです。エレキギターでソロや速弾きをする場合は、厚め(1.0mm以上)が正確なアタックを生みます。バランスを取りたい人には、0.73mmや0.88mmの中厚タイプがおすすめです。厚さ選びで演奏の快適さが大きく変わります。
スタイル別・目的別のピック選び

アコースティックギターに合うピック
アコースティックギターでは、柔軟性のある薄めのピックが向いています。特に0.6mm以下のティアドロップ型は、コードストローク時に弦との摩擦が自然で、温かみのあるサウンドを出せます。素材はナイロンやセルロイドが定番で、柔らかく優しいトーンが特徴です。ストロークのリズム感を重視する方には、少し滑りにくいトーテックス製もおすすめです。
エレキギターに合うピック
エレキギターでは、厚めのピックを選ぶと安定したピッキングができます。1.0mm前後の硬い素材(トーテックスやウルテムなど)は、リードプレイや速弾きでの精度が高く、音の輪郭も明確です。特にジャズ型のピックは、先端が尖っているため細かいフレーズが弾きやすいです。ロックやメタルを演奏する方は、硬くて滑らない素材を選ぶと良いでしょう。
弾き語り・伴奏向けピック
弾き語りでは、ストロークの柔らかさと安定性が求められます。中厚(0.7〜0.8mm)のティアドロップ型が最適で、軽いタッチでコードを弾いても自然な響きになります。素材はナイロンやコットン混合タイプなど、少し柔らかめの質感が弾き心地を向上させます。グリップ付きのピックを選ぶと、汗をかいても滑りにくく安定したストロークが可能です。
特殊用途:ジャズ・ベース・サムピックなど
ジャズやブルースでは、硬めのピックを使用して明瞭なアタックを出すのが主流です。ベースギターには、厚さ1.2mm以上の大型トライアングル型が安定します。また、親指にはめて使うサムピックは、アコギやカントリー演奏で便利なアイテムです。演奏スタイルや楽器に合わせてピックを使い分けることで、音色と表現の幅が広がります。
初心者におすすめの定番ピックブランド・モデル

Fender(フェンダー)セルロイドピック
世界的ギターブランド「Fender(フェンダー)」が手がけるセルロイドピックは、初心者からプロまで幅広く愛用されています。程よいしなやかさと柔らかいアタックが特徴で、コードストロークにも単音弾きにも対応できる万能モデルです。カラーや厚さのバリエーションも豊富で、演奏スタイルに合わせて選べます。特に「ミディアムゲージ(0.73mm前後)」は扱いやすく、最初の1枚としておすすめです。
Jim Dunlop(ジムダンロップ)トーテックスシリーズ
Jim Dunlopはピック業界で最も有名なブランドの一つです。トーテックスシリーズは、耐久性と滑りにくさを両立した定番モデルで、多くのプロギタリストも愛用しています。表面のマットな質感が指にフィットし、汗をかいても滑らないため、長時間の演奏にも最適です。カラーによって厚さが一目で分かるのも便利なポイント。迷ったらまずこのシリーズを試してみる価値があります。
Clayton/D’Andrea/Ibanezなど個性派ブランド
クレイトン(Clayton)は厚みがありながら軽量で、ロックやジャズプレイヤーに人気です。D’Andreaは歴史あるブランドで、ヴィンテージサウンドを重視するギタリストから支持されています。Ibanezのピックは、シャープな先端形状が特徴で速弾きに向いています。それぞれ異なる個性を持っており、自分の演奏スタイルに合ったブランドを探す楽しみもあります。
初心者が最初に選ぶべき「無難な1枚」
これからギターを始める人には、0.73mmのトーテックス・ティアドロップ型がおすすめです。薄すぎず厚すぎず、ストロークと単音どちらにも対応できます。最初は“標準的な1枚”から始め、徐々に厚さや素材を変えて試していくのが上達への近道です。
ギターピックは消耗品なので、複数のタイプを持って弾き比べることで、自分の感覚に合うものを見つけやすくなります。
ピックの正しい持ち方・使い方

基本の持ち方と角度
ピックは「親指と人差し指で軽く挟む」のが基本です。持ち方が強すぎると音が硬くなり、力みの原因になります。親指の腹でピックを押さえ、人差し指の側面で支えるように持ちましょう。ピックの先端は2〜3mmほど出して、弦に対して約15〜30度の角度で当てると、自然な音が出ます。正しい角度で弾くと、ピッキングの抵抗が減り、滑らかなストロークが可能になります。
ストローク・アルペジオでのピッキング角度の違い
ストローク演奏では、ピックをやや斜めにして“撫でるように”弾くと、柔らかく温かみのある音になります。一方、アルペジオやリード演奏では、弦にしっかりと当てることで、クリアで力強いトーンが得られます。演奏スタイルによって角度を調整する意識を持つと、表現の幅が広がります。ピックは単なるツールではなく、“音の筆先”として扱うイメージを持つと良いでしょう。
ピックが滑る場合の対策
ピックが滑る原因は、表面の素材と指の湿気の影響によるものが多いです。対策として、滑り止め加工付きのピック(例:Jim DunlopのGripシリーズ)を選ぶか、指先を軽く湿らせてから持つ方法があります。滑りにくいマット加工やドットグリップ付きモデルも人気です。また、ピック表面を軽く紙やすりで擦ることで、自作の滑り止めを作ることも可能です。
ピックが欠ける・削れる原因と対処法
ピックが頻繁に欠ける場合、弦への当て方が強すぎる可能性があります。弦を“弾く”より“流す”感覚でピッキングすると、摩耗が少なくなります。また、角が丸くなったピックは音がこもる原因になるため、定期的な交換が必要です。厚さが薄いピックは消耗が早いため、練習用には中厚〜厚めを選ぶとコスパが良くなります。ピックは定期的にチェックしておきましょう。
ピックのメンテナンスと保管方法

ピックの寿命と交換の目安
ピックは見た目以上に消耗が早いアイテムです。角が丸くなったり、先端が削れて引っかかるようになったら交換時期のサインです。素材によって寿命は異なりますが、ナイロン製で2〜3週間、トーテックス製で1〜2カ月が目安です。練習頻度が高い人ほど消耗が早くなるため、常に予備を持っておくと安心です。演奏ごとにピックの状態を確認しましょう。
ピックを長持ちさせる保管のコツ
ピックは小さいため、失くしたり曲がったりしやすいです。保管には専用のピックケースやピックホルダーを使用しましょう。財布やポケットに入れっぱなしにすると変形や折れの原因になります。温度や湿度にも注意が必要で、特にセルロイド製ピックは高温で変形しやすいので直射日光を避けて保管します。整頓された状態で持ち運ぶことが長持ちの秘訣です。
素材別メンテナンス(セルロイド・ナイロンなど)
セルロイド製は水や湿気に弱いため、使用後は乾いた布で拭き取ると劣化を防げます。ナイロン製やトーテックス製は比較的丈夫ですが、汗や油分が残ると滑りやすくなるため、同様に軽く拭いて保管するのがベストです。メタルやアクリルピックは中性洗剤で軽く洗浄可能です。素材ごとの特性を理解してケアすることで、ピックの寿命を延ばせます。
ピック選びでよくある失敗と回避法

「見た目」で選んで弾きにくい
初心者によくある失敗は、デザインだけでピックを選んでしまうことです。カラフルでおしゃれなピックは魅力的ですが、素材や厚さが合わないと演奏が難しくなります。まずは機能性を優先して選び、慣れてから好みのデザインに変えるのが良いでしょう。見た目と実用性を両立できるブランドも多いので、試奏を重ねて自分に合った1枚を見つけましょう。
用途に合わないピックを選ぶ
ピックは「どんな演奏をするか」で選ぶ必要があります。ストローク中心の人が厚いピックを使うと音が強すぎて不自然になり、逆にリード中心の人が薄いピックを使うと音がぼやけがちです。自分の演奏スタイルを明確にしたうえで、最適な厚さ・形・素材を選ぶことが大切です。演奏スタイルに合わないピックを使うと、フォームや音作りにも悪影響を与えます。
同じピックを使い続けることでの弊害
「気に入ったピックを何年も使い続けている」という人も多いですが、ピックは消耗品です。長く使うと、知らぬ間に角が摩耗し、音の輪郭が曖昧になります。定期的に新品と弾き比べてみると、音の明瞭さが全く違うことに気づくはずです。お気に入りのピックを複数枚ストックし、ローテーションで使うことで、常にベストな音を保てます。
ピックを使いこなす応用テクニック

複数ピックを使い分ける
上達してくると、1枚のピックだけでは表現に限界を感じることがあります。たとえば、ストローク用には薄めのピック、ソロ演奏や速弾き用には厚めのピックを使い分けるのがおすすめです。曲ごとにピックを変えることで、音の粒立ちやニュアンスを自在にコントロールできます。ジャンルごとに複数のピックを持っておくと、演奏の幅がぐっと広がります。
ピックの角度・持ち方を意識して音色を変える
ピックの角度を少し変えるだけで、音の印象は大きく変化します。ピックを弦に対して斜めに当てると柔らかく温かい音に、垂直に当てると力強く歯切れのよいサウンドになります。持ち方も重要で、親指と人差し指の力加減を調整することでアタック感を自在にコントロールできます。ほんの数ミリの変化が音質を変える“魔法”になるのが、ピックの奥深いところです。
自作・カスタムピックに挑戦
自分好みのピックが見つからない場合は、オリジナルピックを作るのも楽しい選択肢です。専用のカッターや研磨用ペーパーを使えば、厚さや形状を自由にカスタマイズできます。素材にこだわるなら、アクリル板や木材を使うのもおすすめです。さらに、業者によるオーダーピック制作サービスでは、名前入りやロゴ入りのデザインも可能。自作ピックは愛着がわき、演奏モチベーションも高まります。
ピックアクセサリー活用(ピックホルダー・ケース)
ピックは小さいため、練習中やライブ中に失くしがちです。ピックホルダーを使えば、ギターのヘッドやストラップに簡単に装着でき、演奏中の交換もスムーズです。また、複数のピックを収納できるケースを持っておくと、厚さや素材をすぐに変えて試せます。ピックは日々の練習で最も消耗するアイテムだからこそ、アクセサリーを上手に活用することが重要です。
ピックを通じて見えてくる「音の個性」
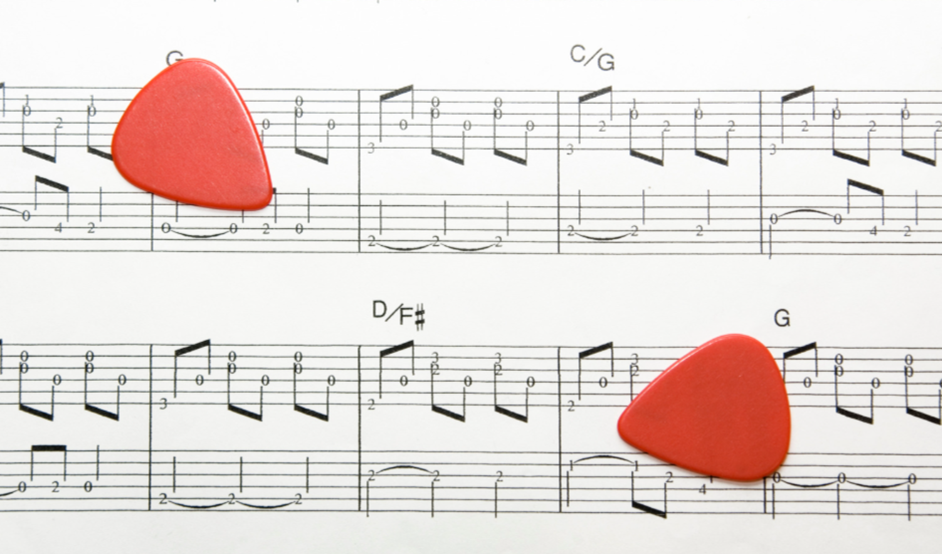
音楽スタイルごとにピックが語る個性
ギタリストにとってピックは“声”とも言える存在です。ロックでは硬くて鋭いピックで力強いリフを、ジャズでは丸みのあるピックで柔らかいトーンを奏でます。クラシックやアコースティックでは、薄めのピックが繊細な表現をサポートします。自分の音楽スタイルを理解し、それに合ったピックを使うことで、音に“あなたらしさ”が宿るようになります。
ピックで生まれる「タッチの違い」を体感する
ピックを変えるだけで、同じギター・同じアンプでもまったく違う音色になります。薄いピックでは軽快で明るいトーン、厚いピックでは低音の締まりと音の太さが増します。素材の違いも音に影響し、ナイロンは柔らかく、ウルテムは硬質でシャープなサウンドになります。演奏者がピックのタッチを意識することで、音楽に繊細なニュアンスが生まれるのです。
有名ギタリストとピックの関係
実は多くの有名ギタリストも、ピック選びには強いこだわりを持っています。エリック・クラプトンはセルロイド製、ジョン・ペトルーシは厚めのジャズ型、スティーヴ・ヴァイはグリップ付きピックを使用するなど、それぞれのプレイスタイルに合わせて選んでいます。彼らの音を真似したい場合は、同じブランドや厚さのピックを試してみるのも良い練習方法です。
ピック選びが上達に直結する理由
ピックは単なる消耗品ではなく、「音作りの第一歩」です。手に馴染むピックを使えば、無駄な力が抜けてピッキングが安定し、上達スピードが格段に上がります。逆に合わないピックを使うと、弦に引っかかる感覚が残り、フォームが崩れる原因になります。自分にぴったりのピックを見つけることは、ギターを長く楽しむための最も大切な習慣です。
ピック選びをより楽しむためのヒント

お気に入りの「音」を見つける試奏法
同じピックでも、ギターの種類やアンプの設定で音は変わります。購入前に必ず弾き比べを行いましょう。最初はコードストローク、次に単音、最後にアルペジオを試すと、音の違いを感じやすいです。ピックを変えながら録音して比較するのもおすすめ。自分の耳で「一番しっくりくる音」を探すプロセスが、上達の近道です。
練習の中でピックを“育てる”感覚を持つ
長く同じピックを使うと、指や弦との馴染みが生まれ、自然と音がまとまっていきます。新品のピックよりも少し削れた状態のほうが、柔らかい音を出せることもあります。ただし、摩耗が進みすぎると音が不安定になるため、頃合いを見て交換することが大切です。ピックは使い捨てではなく、自分のタッチを育てる“相棒”だと考えましょう。
ピックは「弾く」より「響かせる」ための道具
ピックを強く弾きつけるのではなく、弦の上を滑らせるように扱う意識が大切です。力を抜いて弾くことで音が自然に広がり、ピッキングの表情が豊かになります。特にアコースティックギターでは、ピックの角度とスナップを意識することで、プロのような深みのあるサウンドを出せます。弾くより「鳴らす」意識を持つことが、ピック上達の鍵です。
自分だけのピックコレクションを作る
さまざまなブランド・素材・厚さのピックを試して、自分だけの“お気に入りセット”を作るのも楽しいです。ライブ用・練習用・録音用など用途に応じて使い分けると、音作りの幅が広がります。ピックは安価で種類も豊富なので、定期的に新しいタイプを試す習慣をつけると良いでしょう。小さな変化が、大きな音の違いを生みます。
まとめ — 自分に合うギターピックを見つけよう

記事全体のポイント
ギターピックは「形状・厚さ・素材」によって弾き心地や音質が大きく変わります。初心者はまず中厚のティアドロップ型から始め、徐々に他のタイプを試すのが理想です。ピックの角度や持ち方、メンテナンスを意識するだけで音の安定感が増し、演奏の表現力も向上します。たった1枚のピックが、あなたのギターサウンドを劇的に変えるのです。
今日からできるピック選びの実践ステップ
- 厚さの違う3種類(薄・中厚・厚)を試す
- ストロークとリード両方で弾き比べる
- 音の違いを感じ、自分の手に最も馴染むものを選ぶ
これを繰り返すことで、自然と「自分の音」に近づいていきます。ピック選びは一度きりではなく、成長とともに変化するもの。常にアップデートを意識しましょう。
最後に — ピック選びは“音作り”の第一歩
ピックは最も身近で奥深い音作りのツールです。小さな変化が大きな結果を生むことを、ぜひ体感してみてください。あなたにぴったりのピックを見つけることができれば、演奏の楽しさは何倍にも広がります。
アサヒ音楽教室では、初心者の方から経験者まで、それぞれの演奏スタイルに合わせたギターレッスンを行っています。ピックの選び方や正しい持ち方、音の出し方まで、講師が丁寧にサポート。オンラインでも対面でも受講可能です。まずは無料体験レッスンで、あなたの「理想の音」を一緒に見つけてみませんか?
関連記事
-

2026年2月16日
講師ブログピアノ教室の体験レッスンは何を見る?後悔しないためのチェックポイントと失敗しない先生の選び方完全ガイド
ピアノ教室の体験レッスンへ行く前に知っておきたい基礎知識 ピアノ教室選びで「体験」が最も重要視される理由 ピアノという楽器は、他の習い事と比較しても講師と生徒が一対一で向き合う時間が非常に長いのが特徴...
-

2026年2月16日
講師ブログ楽器演奏は最高の「脳の筋トレ」!ストレス解消から認知症予防まで驚きの効果を徹底解説
音楽を趣味にするメリットとは?人生の質(QOL)が劇的に変わる理由 日々の仕事や家事に追われ、ふと「自分を豊かにする時間が足りない」と感じることはありませんか。ストレス社会と呼ばれる現代において、心の...
-

2026年2月16日
講師ブログ音楽教室の振替は無料が安心!後悔しない選び方と回数・期限・注意点を徹底解説【2026年最新ガイド】
急な予定変更や体調不良…月謝を無駄にしたくない方へ 音楽教室に通い始める際、多くの方が抱く不安の一つが「急な予定が入ったときにレッスンはどうなるのか」という点です。仕事での残業や急な出張、あるいは自分...
Blog 講師ブログ
-
2026年2月16日
音楽教室の振替は無料が安心!後悔しない選び方と回数・期限・注意点を徹底解説【2026年最新ガイド】
急な予定変更や体調不良…月謝を無駄にしたくない方へ 音楽教室に通い始める際、多くの方が抱く不安の一つが「急な予定が入ったときにレッスンはどうなるのか」という点です。仕事での残業や急な出張、あるい...
-
2026年2月16日
ピアノ教室の体験レッスンは何を見る?後悔しないためのチェックポイントと失敗しない先生の選び方完全ガイド
ピアノ教室の体験レッスンへ行く前に知っておきたい基礎知識 ピアノ教室選びで「体験」が最も重要視される理由 ピアノという楽器は、他の習い事と比較しても講師と生徒が一対一で向き...
-
2026年2月16日
楽器演奏は最高の「脳の筋トレ」!ストレス解消から認知症予防まで驚きの効果を徹底解説
音楽を趣味にするメリットとは?人生の質(QOL)が劇的に変わる理由 日々の仕事や家事に追われ、ふと「自分を豊かにする時間が足りない」と感じることはありませんか。ストレス社会と呼ばれる現代...
Course コース一覧
Area スタジオエリア一覧
| 東京23区 |
|---|
| 東京23区外 |
|---|
| 神奈川県 |
|---|
| 千葉県 |
|---|
| 埼玉県 |
|---|


