Blog 講師ブログ
2025年10月24日
【作曲初心者完全ガイド】1曲を作る7ステップと練習法
はじめに:作曲初心者に知っておいてほしいこと

なぜ“作曲”がゼロからでも始められるのか
作曲は、特別な才能や音楽理論の深い知識がなくても始めることができます。近年はDTM(デスクトップミュージック)環境が整い、パソコンやスマートフォンだけで楽曲制作が可能です。作曲初心者の方は、最初から完璧を目指さず、「まず1曲完成させる」ことを目標にすると良いでしょう。楽しみながら作る経験こそが、上達への最短ルートです。
本記事で学べることと読者メリット
この記事では、作曲初心者が最初の1曲を完成させるための具体的な手順や考え方を、分かりやすく紹介します。メロディやコード進行の作り方、リズムの付け方、歌詞の乗せ方、DTMの基礎など、必要な知識をすべて一通りカバーしています。この記事を読み終えるころには、「何から始めれば良いか」が明確になり、自分の力で楽曲を完成させられる自信がつくはずです。
“作曲 初心者”で検索する人が抱える悩み・疑問
作曲を始めたいけれど、「何から手をつければいいかわからない」「メロディが思いつかない」「コードが難しそう」と感じる方は多いです。さらに「DAWソフトの使い方が難しそう」「音感がないから無理かも」と不安を抱く人も少なくありません。この記事では、そうした悩みを一つひとつ解決しながら、作曲初心者が“最初の一曲”を完成できるように導きます。
作曲の全体像をつかもう(初心者向けロードマップ)

作曲で扱う要素(メロディ・コード・構成・リズム・アレンジ)
作曲は、いくつかの要素の組み合わせで成り立っています。中心となるのは「メロディ」ですが、支える「コード進行」や「リズム」、「曲全体の構成(Aメロ・Bメロ・サビなど)」も重要です。さらに、仕上げとして「アレンジ」や「ミックス」を行い、完成度を高めます。初心者のうちは、これらをすべて完璧に理解しようとせず、「メロディとコード」から始めるのがポイントです。
7ステップで“曲を完成させる”流れ
作曲初心者でも実践しやすい方法として、「7ステップ作曲法」をおすすめします。
①参考曲を決める
②テーマとコード進行を設定
③メロディを作る
④曲構成を組む
⑤歌詞をつける
⑥簡単なアレンジ
⑦ラフミックスと完成
この流れを守ることで、迷わずに進めることができます。順序を明確にすることで、作曲プロセスがぐっと楽になります。
まずは短時間で“作品を出すこと”を最優先に
最初は「完成度よりも完成数」が大切です。完璧を求めて途中で止まってしまうより、多少粗くても1曲作り切る方が、得られる学びは多いのです。作曲初心者のうちは、数をこなして感覚をつかむことを意識しましょう。1曲を作るごとに、自分の作風や得意なコード進行、好きなメロディパターンが見えてきます。完成を重ねることで、自然と上達していきます。
ステップ1:リファレンス曲を決めて方向性を定める

リファレンス選びのポイント(ジャンル・BPM・構成)
作曲初心者にとって、最初に「どんな曲を作りたいか」を決めるのは重要です。参考にするリファレンス曲を1曲選び、その曲のジャンルやテンポ(BPM)、構成を分析します。ポップス、ロック、バラード、EDMなど、方向性を決めるだけで、作業の迷いが減ります。好きなアーティストの曲を参考にするのも効果的です。
参考にしすぎないための「差別化視点」
リファレンスは参考にするものであって、コピーするものではありません。大切なのは、「どの要素を参考にし、どこを自分らしく変えるか」を意識することです。例えば、メロディの雰囲気は真似ても、リズムやコードを変えるだけでオリジナリティが生まれます。作曲初心者は“模倣から学び、違いで勝つ”ことを意識しましょう。
参考曲との比較で自分の作風を固める
1曲を完成させたら、リファレンス曲と聴き比べてみましょう。構成、テンポ、メロディライン、リズムなどの違いを客観的に確認することで、自分の作曲スタイルが見えてきます。初心者のうちは“分析力”も上達の鍵です。リファレンスを活用し、自分なりの作風を確立していくことが、作曲の継続にもつながります。
ステップ2:キー選定とコード進行入門

キー(調)の基本と決め方
キーとは、曲の「基準となる音の高さ」です。作曲初心者は、まずCメジャー(ハ長調)から始めるのがおすすめ。ピアノで白鍵だけを使うため、理論がわからなくても扱いやすいのです。歌モノの場合は、歌いやすい高さを基準にキーを選ぶと良いでしょう。メジャーキーは明るく、マイナーキーは切ない印象を作りやすいという特徴も覚えておくと便利です。
初心者が使いやすい定番コード進行5選
作曲の中核を担うコード進行は、初心者がつまずきやすい部分です。しかし「定番進行」を知れば一気に楽になります。王道進行はC–G–Am–F(I–V–vi–IV)とその回転形(Am–F–C–G、F–G–C–Am、C–Am–F–G)です。これらは“王道進行”と呼ばれ、多くのヒット曲でも使われています。作曲初心者は、この中から好きなパターンを選んで試してみましょう。
コード進行で曲の印象を変えるコツ
コード進行を少し変えるだけで、曲の雰囲気は大きく変化します。たとえば、C–Am–F–Gは柔らかく優しい印象に、Am–F–C–Gは切なさを強調します。作曲初心者は、進行を変えるたびにメロディの印象がどう変化するかを確認することで、感覚的な“音感”が身についていきます。理論よりも「聴いて感じる」姿勢を大切にしましょう。
ステップ3:メロディの組み立て方(初心者でもできる)

リズム先行 or 音程先行、どちらから始めるか
作曲初心者がメロディを作るとき、多くの人が「音をどう並べるか」で悩みます。おすすめは“リズム先行”です。まずはドラムや手拍子を使い、リズムに合わせて鼻歌を口ずさんでみましょう。メロディの土台は、音程よりもリズム感にあります。リズムに乗せたフレーズから自然とメロディが生まれることが多いのです。音の高さは後から調整して構いません。
2小節+2小節のフレーズ構造の作り方
メロディは、長いものを一気に作るよりも、短い2小節単位で考えると簡単です。最初の2小節で“問い”を作り、次の2小節で“答え”を返すような形を意識しましょう。この「4小節ひと塊」構成は多くのポップスに使われています。作曲初心者は、ピアノロールや楽器アプリを使って簡単なリズム+音程の繰り返しからスタートするのがおすすめです。
繰り返しと変化で“耳に残る”メロディを作る
ヒット曲のメロディは、必ず“繰り返し”と“変化”のバランスが取れています。まったく同じフレーズを繰り返すと飽きられ、変化しすぎると覚えにくくなります。作曲初心者は「3回繰り返して4回目だけ少し変える」程度がちょうど良いです。たとえば、最後の音を上げるだけでも印象は劇的に変わります。リズムを少し崩すのも効果的です。
ステップ4:曲構成(A/B/サビなど)を設計する

曲構成の基本パターン3種
ポップスの多くは「Aメロ→Bメロ→サビ」という3部構成を中心に作られています。Aメロで曲の世界観を提示し、Bメロで期待を高め、サビで感情を爆発させる流れです。作曲初心者はこの王道パターンから始めるのが安心です。短いインストゥルメンタル曲の場合は、A–B–AやA–B–C型でも構いません。構成は物語のように流れを意識しましょう。
盛り上げポイントの考え方(メロ/コード密度変化)
作曲では“どこで盛り上がるか”が非常に大切です。サビを強調するためには、Aメロとサビの音域差をつけるのが効果的です。また、コードの変化を増やす、リズムを細かくする、楽器の数を増やすなどの手法もあります。作曲初心者は「盛り上げをどこで作るか」を先に決めてからメロディを構築すると、まとまりのある楽曲になります。
構成設計時の注意点(単調になる・冗長になる)
曲が単調に感じる最大の原因は、「構成の変化が少ないこと」です。AメロとBメロが同じテンポ・同じメロディでは、聴き手が飽きてしまいます。逆に、変化を入れすぎると全体がまとまらなくなることもあります。作曲初心者は「1つの要素だけ変える」ことを意識してください。メロディかリズム、どちらか一方を変えるだけで十分です。
ステップ5:歌詞・言葉を乗せる技術

キラーワード・テーマの決め方
作曲初心者が歌詞を書く際は、まず「テーマ」や「感情」を1つに絞ることが大切です。恋愛、挑戦、夢、別れなど、具体的なモチーフを決めましょう。そして、その中で“キラーワード”を設定します。たとえば「会いたい」「戻れない」「信じたい」など、感情を象徴する言葉を中心に構成すると、歌詞全体が一貫して響くようになります。
歌詞とメロディのアクセント合わせ方
メロディと歌詞を組み合わせるときは、「強拍(アクセント)」を意識しましょう。たとえば、4拍子の1拍目に重要な言葉を置くと自然に印象が残ります。作曲初心者は、まずメロディに仮の“ラララ”を乗せ、発音しやすいリズムを見つけてから言葉を当てはめていくとスムーズです。無理に押し込まず、言葉がメロディに“乗る”感覚をつかみましょう。
歌詞の語数バランスと母音の選び方
日本語の歌詞は、母音の響きが重要です。特に“あ・い・う・え・お”の中でも、“あ・お”は明るく、“い・え”は切なく響く傾向があります。曲の雰囲気に合わせて母音の多い言葉を選ぶと、より自然で印象的になります。また、語数が多すぎるとリズムが詰まり、少なすぎると間延びします。作曲初心者は、1小節に4〜8音程度を目安にすると良いでしょう。
ステップ6:最小限アレンジで曲を形にする

ドラム・ベースの基本パターン配置
アレンジを始めるとき、まずはリズムセクションから作るのが基本です。ドラムは「キックが1拍目、スネアが2・4拍目」という定番配置でOKです。ベースはコードのルート音を中心に、ドラムと同じリズムを刻むようにしましょう。作曲初心者でも、無料のループ素材を使えば簡単に“それっぽい”サウンドを作れます。重要なのは“グルーヴ感”を意識することです。
コードストリングス・パッドなどの補助楽器入門
次に、曲の雰囲気を支える楽器を重ねます。ピアノやギター、ストリングス、パッド音などを使うと音に厚みが出ます。作曲初心者は、まず「コードを鳴らす楽器」と「リズムを支える楽器」の2種類だけでも十分です。パートを増やしすぎると音が濁るため、最初はシンプルに仕上げましょう。少ない音数でもバランスが取れると完成度が上がります。
ミックス前提で音量構成を意識する
アレンジ段階で音量バランスを意識することは、後のミックスを楽にします。ボーカルが主役の場合は、他の楽器の音を控えめにし、声が埋もれないように調整します。作曲初心者は、各トラックの音量を目で見て揃えるより、耳で聴いて判断することを重視してください。最初は難しく感じるかもしれませんが、少しずつ感覚が磨かれていきます。
ステップ7:ラフミックスと書き出しで“完成”させる

音量バランス/パンニングの基礎
ラフミックスとは、完成前の“仮仕上げ”の段階を指します。ここで重要なのは、音量バランスとパンニング(左右配置)です。ボーカルは中央、ドラムはやや広め、ギターや鍵盤は左右に振ると奥行きが生まれます。作曲初心者は、ステレオ感を意識して配置するだけで、驚くほどプロっぽい印象になります。
EQ・コンプレッサーを簡単に使う方法
EQ(イコライザー)は音の不要な部分を削るツールです。ベースなら低域を残し、ボーカルなら中高域を強調するとクリアに聴こえます。コンプレッサーは音量のムラを整える効果があります。作曲初心者は“プリセット”を活用して感覚をつかみましょう。細かい設定よりも、「聴きやすくなったか」を耳で確認するのが第一歩です。
書き出しフォーマットと共有方法
ミックスが終わったら、音源を書き出して完成です。WAV形式は高音質、MP3形式は共有に便利です。作曲初心者はまずMP3でSNSや友人に聴かせるところから始めましょう。反応をもらうことで、モチベーションも上がります。曲を公開することは、次の成長への第一歩です。恐れず“外に出す勇気”を持つことが大切です。
30日で上達できる練習スケジュール(初心者向け)

Week1:4コードで8小節のループを作る
作曲初心者が最初に身につけるべきは、シンプルな“8小節ループ”を作る力です。まずは定番のコード進行(C–G–Am–Fなど)を選び、ループ再生してみましょう。その上に鼻歌でメロディを乗せてみることで、自然とメロディ感覚が養われます。まだ完成を目指さず、音のつながりを感じることが目的です。繰り返すうちに「好きな響き」が明確になります。
Week2:A/B/サビを構築して仮歌詞を作る
2週目は、曲の構成を組み立てる段階です。Aメロでは静かに始まり、Bメロで盛り上げ、サビで最高潮にするのが基本です。コード進行を変えずに、メロディだけで強弱をつける練習をしましょう。また、仮の歌詞でも構いませんので、テーマに沿った言葉を入れると曲の世界観が固まります。作曲初心者でも、ここで「物語の流れ」を意識できるようになります。
Week3:ベースとドラムを加えてアレンジに挑戦
3週目は、リズムセクションを加えて曲を形にしていきます。ドラムはシンプルに4拍、ベースはコードのルート音を中心に打ち込みましょう。打ち込みが難しい場合は、DAW内のループ素材を活用しても構いません。作曲初心者にとって重要なのは“雰囲気を作る”こと。音が重なり合って“楽曲になっていく感覚”を体感する週です。
Week4:ミックス・書き出し・振り返り
最終週は、完成させるフェーズです。音量バランスを整え、リファレンス曲と聴き比べながら微調整を行いましょう。完成後は客観的に聴く時間を設け、「良い点」「改善点」をメモします。作曲初心者が上達する最大のポイントは“振り返ること”。1曲ごとに課題を言語化すれば、次の作品では確実にレベルアップします。
毎日15〜30分でできる練習例
作曲は一度に長時間やるよりも、毎日少しずつ取り組む方が効果的です。たとえば「月曜はコード練習」「火曜はメロディ作り」「水曜は歌詞」「木曜は構成」「金曜はアレンジ」「土曜はミックス」「日曜は復習」といったリズムで習慣化してみましょう。作曲初心者でも1か月で“曲作りの全体像”を体で覚えることができます。
よくある悩みと最短解決ガイド

メロディが浮かばないときの打開策
何も思い浮かばないときは、いったん“鼻歌”を録音してみましょう。無意識のメロディが意外と良い素材になることがあります。また、作曲初心者は「コードを鳴らしながらリズムを刻む」方法もおすすめです。音程よりリズムに注目すると、自然とメロディの骨格が浮かび上がります。最初は「歌詞なし・意味なし」でOKです。大切なのは“流れを止めない”ことです。
似たような曲になってしまうときの対処法
作曲初心者の多くが陥るのが「どの曲も似てしまう」問題です。これを防ぐには、使うコードを1つ変える、テンポを上下させる、またはリズムのアクセントをずらすのが効果的です。また、他ジャンルのリファレンス曲を聴いて分析するのもおすすめです。たとえばポップスにジャズのコードを混ぜるだけで、ぐっと個性的になります。
機材選びで迷ったときの絞り込み基準
DTM環境を整えるときは、まず“最小構成”で始めましょう。パソコンと無料DAW(GarageBandやCakewalkなど)があれば十分です。マイクやMIDIキーボードは後から揃えればOKです。作曲初心者は「作る→聴く→直す」のサイクルを早く回すことが上達の鍵です。高価な機材よりも、使いこなせる環境を優先してください。
理論が難しすぎて挫折しそうなとき
音楽理論は“便利なツール”であって、“絶対ルール”ではありません。作曲初心者のうちは、「感覚でOK」と割り切って構いません。必要になったときに少しずつ覚えれば十分です。まずはC–G–Am–Fが鳴らせて、メロディを乗せられるだけで立派な作曲家の第一歩です。理論は後からついてきます。大切なのは「楽しみながら続けること」です。
ジャンル別の“最初の一歩”アプローチ

ポップスで意識すべきポイント
ポップス作曲では“歌いやすさ”と“メロディの覚えやすさ”が最重要です。サビを中心に、誰もが口ずさめるシンプルなフレーズを意識しましょう。作曲初心者は、テンポ100〜120BPMの範囲で作ると扱いやすいです。コード進行はC–G–Am–Fなどの王道を使い、リズムで変化をつけると自然に完成度が上がります。
バラードでの作曲アプローチ
バラードは“間”と“空気感”が命です。ゆっくりしたテンポ(70〜90BPM)で、シンプルなコード進行を選びましょう。作曲初心者は「音を詰め込みすぎないこと」を意識してください。ピアノかギターだけで成り立つ構成が理想です。感情の抑揚をメロディの上下で表現すると、聴き手に深く響く曲に仕上がります。
ロック曲の作り方の基本
ロックでは“エネルギー感”と“グルーヴ”が大切です。コード進行はC–G–D–Aなど力強い構成を使い、ドラムとベースでリズムを前に押し出しましょう。作曲初心者でも、歪んだギターを重ねるだけで迫力のあるサウンドが作れます。メロディはリズムに合わせてシャープに区切るとロックらしさが出ます。リズム主体の発想がコツです。
EDM・Lo-fiなど電子音楽の始め方
EDMやLo-fiを作る場合、まずはドラムループから始めましょう。キックとハイハットのリズムが全体を引っ張ります。作曲初心者は、DAWのテンプレートを使って“雰囲気を作る”ことを優先すると良いでしょう。メロディよりも“質感”と“空気感”で聴かせるジャンルなので、サウンドデザインを楽しむ感覚で進めてください。
クオリティを底上げする初級ミックス講座
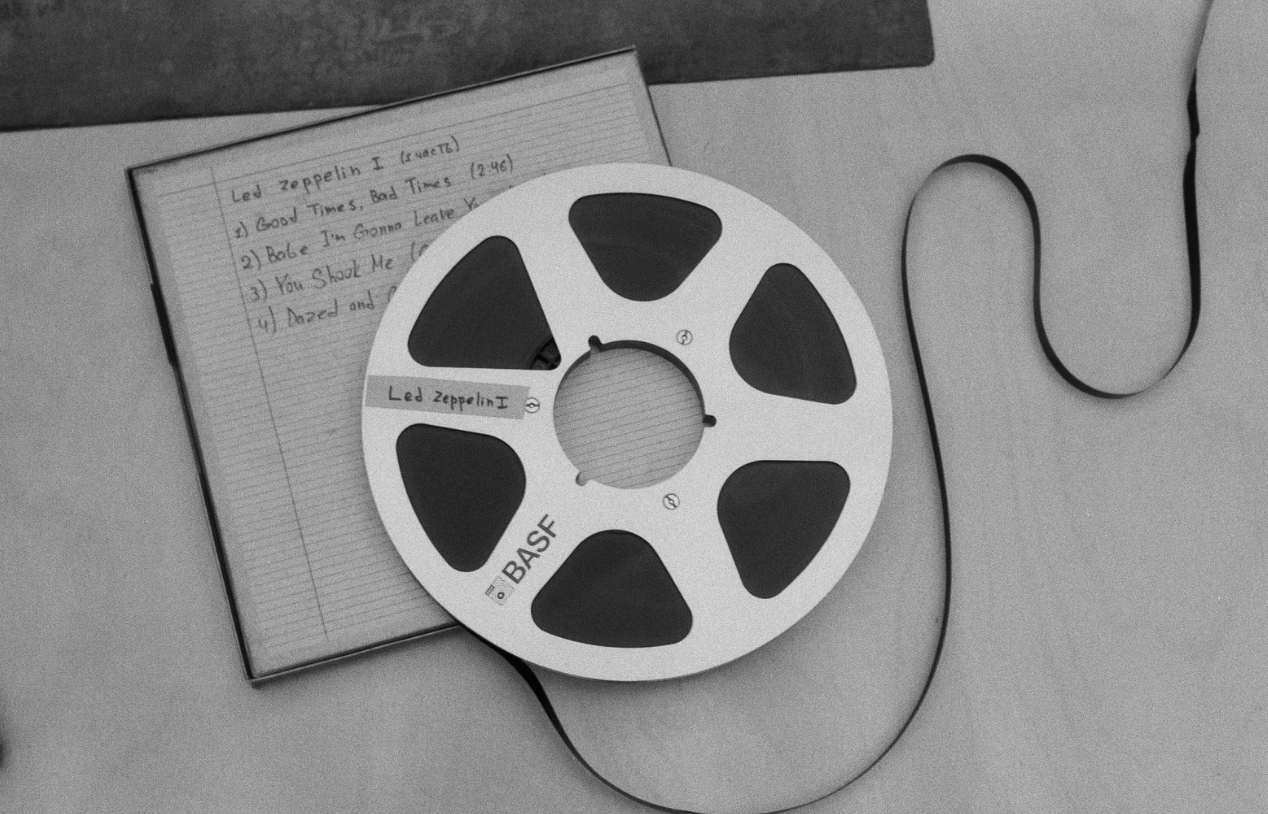
参照音源とのバランスを整える方法
完成した曲をプロの音源と聴き比べると、自分の弱点が一目瞭然になります。音量が小さい、低音が出すぎ、ボーカルがこもっているなどの違いを耳で確認しましょう。作曲初心者は、リファレンス音源をDAWに読み込んで一緒に再生すると、バランスの違いがはっきりわかります。最初は完全に真似るつもりで練習すると、自然に耳が鍛えられます。
EQ・コンプレッサーの使い方のコツ
EQは“整理”、コンプレッサーは“整える”ツールです。EQでは、不要な低域をカットし、ボーカルやメロディの中域を少し持ち上げるとクリアになります。コンプレッサーは大きな音を抑え、小さな音を持ち上げることで全体の安定感を作ります。作曲初心者は難しく考えず、“聴いて心地よいか”を基準に使ってみましょう。
リファレンスとのラウドネス合わせ
自分の曲が小さく感じる場合は、マスタリング段階で音圧を上げる必要があります。Limiter(リミッター)を軽くかけるだけで、全体の音量を統一できます。ただし、かけすぎると音がつぶれて不自然になるため注意が必要です。作曲初心者は、リファレンス曲の音量メーターを見ながら「近い数値」を目指す程度で十分です。耳を鍛えるトレーニングにもなります。
無料テンプレート&ワークシートで作曲をスムーズに

4コード進行早見表
作曲初心者が迷いやすい「どんなコード進行を使えばいいのか」という問題を解決するために、まずは“定番の4コード進行”を手元に置きましょう。C–G–Am–FやAm–F–C–Gなどのパターンは、どんなジャンルでも応用可能です。これをプリントして机の横に貼っておくと、作業がぐっとスムーズになります。慣れてきたら自分で少しずつアレンジしていきましょう。
2小節メロディ練習用グリッド
メロディづくりを感覚的に覚えるには、2小節単位の「メロディグリッド」を使うと便利です。たとえば、4拍子×2小節=8拍分のマスを用意し、そこに音符やリズムのパターンを描いてみましょう。作曲初心者は、実際に歌いながら“どの音が気持ち良いか”を確認するのがおすすめです。小さな成功体験を積み重ねることで、自然に作曲センスが育ちます。
7ステップ作曲チェックリスト
1曲を最後まで作るためには、進行状況を見える化することが大切です。
リファレンス選定
コード決定
メロディ
構成
歌詞
アレンジ
ミックス
という7ステップをリスト化してチェックしていきましょう。作曲初心者でも、進捗が目に見えることで達成感が得られ、途中で挫折しにくくなります。毎回同じテンプレートを使うと、制作のリズムが整います。
30日進捗トラッカー
作曲を継続するコツは“可視化”です。1日ごとに「やったこと」「気づいたこと」「次の目標」をメモできるトラッカーを作りましょう。シンプルな表で構いません。作曲初心者の段階では、数よりも“継続”が最重要です。30日後に自分の記録を見返すと、驚くほどの成長を感じられるはずです。音楽ノートをつける感覚で続けてみてください。
よくある質問(Q&A)

Q1. 楽器が弾けなくても作曲できますか?
はい、問題ありません。最近はDAWやスマホアプリで、マウス操作や打ち込みだけで作曲ができます。作曲初心者の多くが楽器未経験から始めています。鼻歌を録音してメロディを作り、コードをDAW内で鳴らすだけでも立派な作曲です。楽器は後から覚えても大丈夫です。大切なのは“音を形にする勇気”です。
Q2. 歌詞とメロディはどちらを先に作るべき?
これはどちらでも構いません。歌モノなら歌詞先でも、インストならメロディ先でも良いです。作曲初心者は、自分が“作りやすい流れ”を見つけることが重要です。歌詞から感情を出すタイプもいれば、メロディから情景を広げるタイプもいます。正解は一つではありません。まず1曲完成させて、自分に合う順番を探していきましょう。
Q3. 一曲にどれくらい時間をかけるのが理想?
最初のうちは、1曲に1週間〜1か月程度で十分です。長く時間をかけすぎると、途中でモチベーションが下がることがあります。作曲初心者は「完成」すること自体をゴールにしてください。作品数が増えるにつれて、スピードもクオリティも自然と上がっていきます。たくさん作ることで“慣れ”が最大の武器になります。
Q4. 独学と音楽教室、どちらが良い?
独学は自由度が高い一方で、壁にぶつかったときに軌道修正が難しいこともあります。音楽教室では、プロ講師のフィードバックを受けながら効率的に学べます。作曲初心者のうちは独学で始め、行き詰まったらレッスンを受けるのがおすすめです。最近ではオンライン教室も充実しており、自分のペースで学べます。
Q5. オリジナリティを出すには?
オリジナリティとは、“組み合わせの工夫”から生まれます。メロディ、コード、リズム、サウンドのどこか一つを変えるだけで、自分らしい曲になります。作曲初心者はまず「好きな曲3つを混ぜてみる」感覚で挑戦してみましょう。個性は意図的に作るより、曲を重ねるうちに自然と現れるものです。
まとめ:まずは“1曲完成”を目指そう
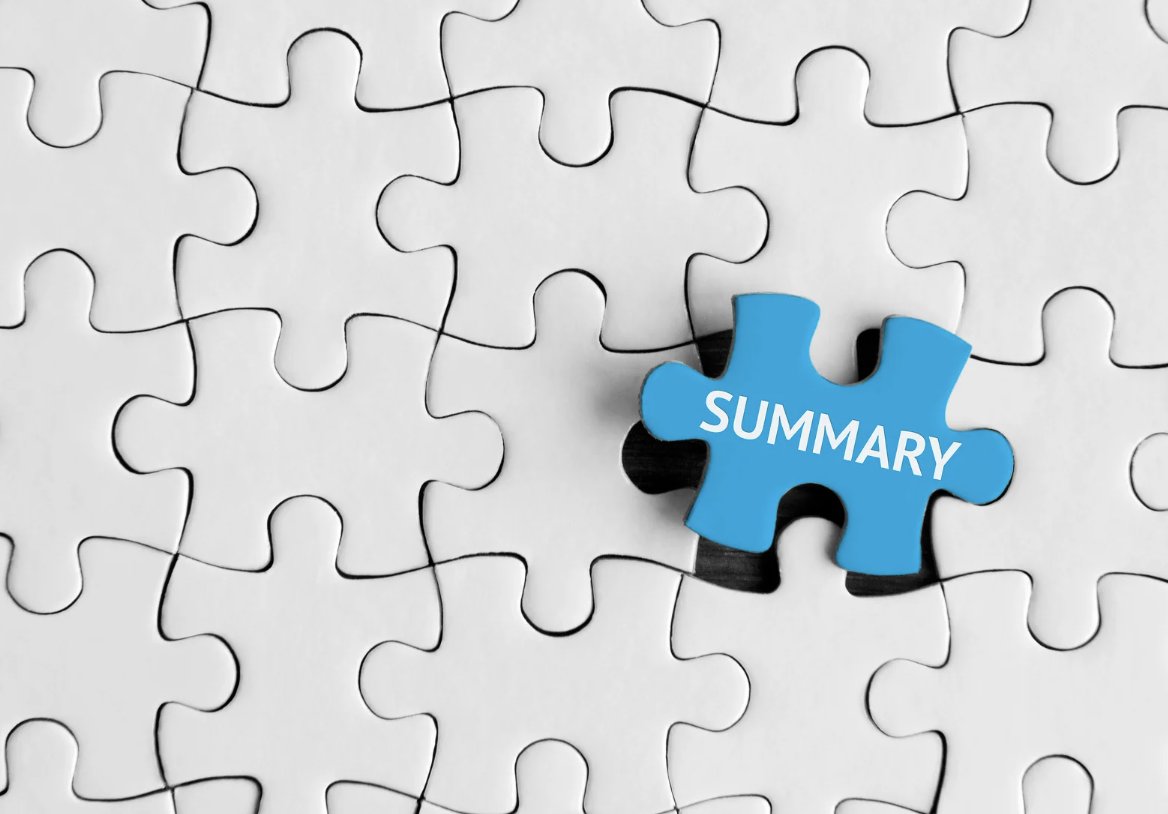
完成させることの意味
作曲初心者が最初に乗り越えるべき壁は、「途中で止まらず1曲を完成させる」ことです。最初の作品は、うまくいかなくて当然です。しかし、形にして初めて次の課題が見えます。音のつながり、メロディの癖、構成の弱点──それらは“完成した曲”からしか学べません。完成はゴールではなく、スタートです。
振り返りと改善のループで上達する
1曲完成したら、数日おいて冷静に聴き直してみましょう。時間を置くことで客観的な視点が得られます。気づいた点をメモし、次の曲に活かす。これを繰り返すだけで、確実にスキルが伸びていきます。作曲初心者の成長速度は驚くほど速く、5曲ほど作るころには自分の“作曲の型”が見えてきます。
次の一歩へ:新しい“型”に挑戦する
1曲完成させたら、次は違うコード進行、違うジャンル、違うテンポで挑戦してみましょう。人は「前と違うこと」に取り組むときに最も成長します。作曲初心者が量産期に入ると、自然とアイデアの引き出しが増え、曲作りが楽しくなっていきます。完璧を求めるより、“続ける仕組み”を作ることが大切です。
作曲を続けるためのモチベーション管理
音楽を作るモチベーションは波があるものです。落ちたときは、無理に作ろうとせず“音楽を聴く時間”を取りましょう。新しい刺激が再び作曲意欲を呼び戻してくれます。SNSに投稿する、小さな目標を立てる、誰かに聴いてもらう──そうした行動が継続の支えになります。作曲初心者ほど、他者の反応が励みになるのです。
最後に:あなたの“はじめての一曲”が未来を変える
どんな大作曲家も、最初の1曲は誰かの真似でした。大切なのは「やってみよう」と思ったその瞬間です。今日から、あなたのメロディが世界にひとつの音になるかもしれません。作曲初心者だからこそ、自由に、恐れず、思いのままに音を紡いでください。失敗を恐れず、完成を積み重ねていくことで、必ず“あなたらしい音楽”が見えてきます。
関連記事
-

2026年2月16日
講師ブログピアノ教室の体験レッスンは何を見る?後悔しないためのチェックポイントと失敗しない先生の選び方完全ガイド
ピアノ教室の体験レッスンへ行く前に知っておきたい基礎知識 ピアノ教室選びで「体験」が最も重要視される理由 ピアノという楽器は、他の習い事と比較しても講師と生徒が一対一で向き合う時間が非常に長いのが特徴...
-

2026年2月16日
講師ブログ楽器演奏は最高の「脳の筋トレ」!ストレス解消から認知症予防まで驚きの効果を徹底解説
音楽を趣味にするメリットとは?人生の質(QOL)が劇的に変わる理由 日々の仕事や家事に追われ、ふと「自分を豊かにする時間が足りない」と感じることはありませんか。ストレス社会と呼ばれる現代において、心の...
-

2026年2月16日
講師ブログ音楽教室の振替は無料が安心!後悔しない選び方と回数・期限・注意点を徹底解説【2026年最新ガイド】
急な予定変更や体調不良…月謝を無駄にしたくない方へ 音楽教室に通い始める際、多くの方が抱く不安の一つが「急な予定が入ったときにレッスンはどうなるのか」という点です。仕事での残業や急な出張、あるいは自分...
Blog 講師ブログ
-
2026年2月16日
音楽教室の振替は無料が安心!後悔しない選び方と回数・期限・注意点を徹底解説【2026年最新ガイド】
急な予定変更や体調不良…月謝を無駄にしたくない方へ 音楽教室に通い始める際、多くの方が抱く不安の一つが「急な予定が入ったときにレッスンはどうなるのか」という点です。仕事での残業や急な出張、あるい...
-
2026年2月16日
ピアノ教室の体験レッスンは何を見る?後悔しないためのチェックポイントと失敗しない先生の選び方完全ガイド
ピアノ教室の体験レッスンへ行く前に知っておきたい基礎知識 ピアノ教室選びで「体験」が最も重要視される理由 ピアノという楽器は、他の習い事と比較しても講師と生徒が一対一で向き...
-
2026年2月16日
楽器演奏は最高の「脳の筋トレ」!ストレス解消から認知症予防まで驚きの効果を徹底解説
音楽を趣味にするメリットとは?人生の質(QOL)が劇的に変わる理由 日々の仕事や家事に追われ、ふと「自分を豊かにする時間が足りない」と感じることはありませんか。ストレス社会と呼ばれる現代...
Course コース一覧
Area スタジオエリア一覧
| 東京23区 |
|---|
| 東京23区外 |
|---|
| 神奈川県 |
|---|
| 千葉県 |
|---|
| 埼玉県 |
|---|


