Blog 講師ブログ
2025年10月15日
ギター楽譜の読み方完全ガイド|初心者でも簡単に読める!

ギターを始めたばかりの方の中には、「楽譜が読めない」「タブ譜と五線譜の違いがわからない」と悩む人が多いでしょう。ギターの楽譜には、タブ譜・コード譜・五線譜といった種類があり、それぞれに読み方のルールがあります。最初は難しく感じるかもしれませんが、ポイントを押さえれば誰でも読めるようになります。
本記事では、ギター初心者の方でも安心して学べるように、楽譜の読み方を基礎から丁寧に解説します。記事を読み終えるころには、タブ譜もコード譜も自信をもって読めるようになり、演奏の楽しさがぐっと広がるはずです。
ギター初心者が楽譜でつまずく理由
なぜ楽譜が難しく感じるのか

ギターの楽譜が難しく感じる一番の理由は、同じ音を複数のポジションで出せるというギター特有の構造にあります。例えば「ド」という音でも、弦やフレットによって押さえ方が異なります。また、楽譜には音の高さや長さ、強弱、奏法など多くの情報が詰まっており、最初はその記号の多さに圧倒されがちです。特にタブ譜と五線譜を併記したスコアでは、情報量が多く混乱してしまうこともあります。しかし、少しずつ構造を理解すれば、楽譜はむしろギター演奏を助けてくれる頼もしい味方になります。
楽譜が読めないとどうなる?
楽譜を読めないまま演奏を続けると、耳コピや動画頼りの練習になりがちです。もちろんそれでも上達はしますが、細かいリズムや表現を再現する力が身につきにくくなります。また、他の楽器奏者と一緒に演奏する際には、五線譜やリードシートを読めないと意思疎通が難しくなることもあります。楽譜を理解していれば、アドリブや作曲にも応用が利き、音楽的な理解力も深まります。楽譜の読み方を身につけることは、ギター演奏の基礎体力を養うことにつながるのです。

ギターで使われる楽譜の種類を知ろう

タブ譜(TAB譜)とは
タブ譜はギター専用に作られた譜面で、6本の線がギターの6弦を表しています。上の線が1弦、下の線が6弦を示します。線上の数字は押さえるフレット番号を意味しており、例えば「3」と書かれていれば、その弦の3フレットを押さえるということです。0は開放弦を表します。タブ譜は音の高さよりも「指の位置」を示すため、初心者でも視覚的に理解しやすく、ギターを始めたばかりの人には最適な譜面です。
コード譜・コードダイアグラムとは
コード譜は、曲のコード進行を中心に記載された譜面です。歌詞の上に「C」「G」「Am」などのコードネームが書かれており、それに合わせて伴奏を弾きます。コードダイアグラムは、指で押さえる位置を図で表したもので、黒丸が押さえる弦、○は開放弦、×は鳴らさない弦を示します。弾き語りをする人にとって、このコード譜は必須の知識です。分数コード(例:G/B)のように、ベース音を変える表記も登場しますが、仕組みを理解すれば難しくありません。
五線譜・リードシートとは
五線譜は、音の高さや長さ、強弱などを最も正確に表せる楽譜です。クラシックやジャズなど、他楽器と合わせて演奏する際には欠かせません。ギターでは五線譜とタブ譜がセットになっているスコアが多く見られます。リードシートは、メロディとコードを簡潔にまとめた譜面で、バンド練習やアドリブ演奏のときに重宝されます。最初は音符の位置関係が難しく感じるかもしれませんが、少しずつ慣れていくと視覚的に音の高さがわかるようになります。
タブ譜の読み方を徹底解説

タブ譜の基本構造
タブ譜の6本の線は、それぞれギターの弦に対応しています。上の線が1弦、下が6弦です。数字は押さえるフレットを表しており、0は開放弦を意味します。例えば、1弦の3フレットに「3」とあれば、最も細い弦の3フレットを押さえて音を出します。複数の数字が縦に並んでいる場合は同時に弾くコードや和音を表し、横に並んでいる場合は順番に弾くメロディを意味します。このように、タブ譜は視覚的に理解しやすく、ギター特有のポジション感覚を身につける助けになります。
リズム記号と音の長さ
タブ譜には音の長さやリズムを表す記号も付けられることがあります。一般的に、五線譜の上に音符が併記されている場合、それがリズムを示しています。4/4拍子や3/4拍子などの拍子記号を確認し、一定のテンポで弾くように意識しましょう。音符には全音符・二分音符・四分音符・八分音符などがあり、それぞれ音の長さを示しています。リズム感をつかむためには、メトロノームを使いながらタブ譜を読む練習をするのが効果的です。慣れてくると、譜面を見るだけでリズムの流れが自然と感じられるようになります。
よく出てくる奏法記号
ギターのタブ譜には、特有の奏法を表す記号が多く登場します。
・「h」
ハンマリングオン
・「p」
プリングオフ
・「/」
スライド
・「b」
チョーキング
これらの記号は、ギターらしい表現を作り出す重要な要素です。ビブラートやミュート、トレモロピッキングなども記号で示されることがあります。最初は難しそうに見えますが、ひとつずつ理解しながら練習していけば自然と読めるようになります。タブ譜を通して、音の表情を豊かに表現できるようになると演奏の楽しさも倍増します。
コード譜の読み方と実践活用
コード譜は、ギター弾き語りや伴奏の際に最もよく使われる楽譜です。歌詞の上に「C」「G」「Am」などのコード名が書かれており、曲の流れに合わせてそのコードを弾いていきます。コード譜はメロディではなく、和音の流れを中心に構成されているため、リズムやテンポを体で感じながら弾くのが大切です。まずは基本コード(C・G・Am・Fなど)を覚え、コードチェンジの練習を繰り返すことで、譜面を見ながらスムーズに演奏できるようになります。
コードダイアグラムの見方
コードダイアグラムは、ギターの指板を縦に見た図形で、指を置く位置を視覚的に示します。図の上に書かれている○は開放弦、×は弾かない弦、黒丸は押さえるポジションを意味します。たとえば「Cコード」なら、5弦3フレット・4弦2フレット・2弦1フレットを押さえます。数字で示される「1〜4」は指番号を意味し、人差し指から小指まで順番に対応します。ダイアグラムを読むことで、コードを正しい形で押さえられるようになり、きれいな音を出すコツがつかめます。
オンコード・分数コードの読み方
コード譜には、「G/B」や「C/G」といった分数コード(オンコード)が登場することがあります。これは、通常のコードに対してベース音を別の音に変更するという指示です。たとえば「G/B」は、Gコードを押さえつつ、ベース音にBを使うという意味になります。オンコードを使うことで、コード進行に滑らかさや奥行きが生まれます。最初は複雑に見えますが、構造を理解すれば難しくありません。演奏に慣れてきたら、オンコードを積極的に使って、より表現力のある伴奏を目指しましょう。
ストローク記号の読み方
コード譜では、リズムを示すためにストローク記号が使われます。
・「↓」
ダウンストローク
・「↑」
アップストローク
・「/」
スラッシュ
他、ストップや空振り(ミュート)を表す記号もあり、曲のグルーヴ感を表現する際に欠かせません。ストローク練習を行う際は、テンポを一定に保ち、リズムの流れを感じながら体全体でリズムを刻むことがポイントです。
五線譜の基礎と読み方
五線譜のルールを理解する

五線譜は、音の高さと長さを明確に示す世界共通の表記方法です。5本の線と4つの間で音の高さを表現し、ト音記号がついている場合はギターで使用する高音域が中心となります。ギターの音域は実際より1オクターブ低く記譜されるため、他の楽器と合わせる際にも調和が取れるようになっています。最初は線と間の位置関係を覚えるのがコツです。たとえば、五線譜上で「ト音記号の第2線」は「ソ」を表し、そこから上下に順に音が並びます。
拍子と小節の読み方
五線譜には、曲のリズムを示す「拍子記号」が書かれています。最も一般的なのは4/4拍子で、1小節に4拍があり、そのうち1拍が四分音符に相当します。3/4拍子はワルツのような三拍子の曲で使われ、6/8拍子は軽やかなリズムの曲に多いです。小節線で区切られた1区間ごとにリズムを感じながら弾くことが大切です。拍子を理解して譜面を読むことで、音の長さを正確に把握できるようになり、曲全体の流れをつかみやすくなります。

休符・付点・タイの見方
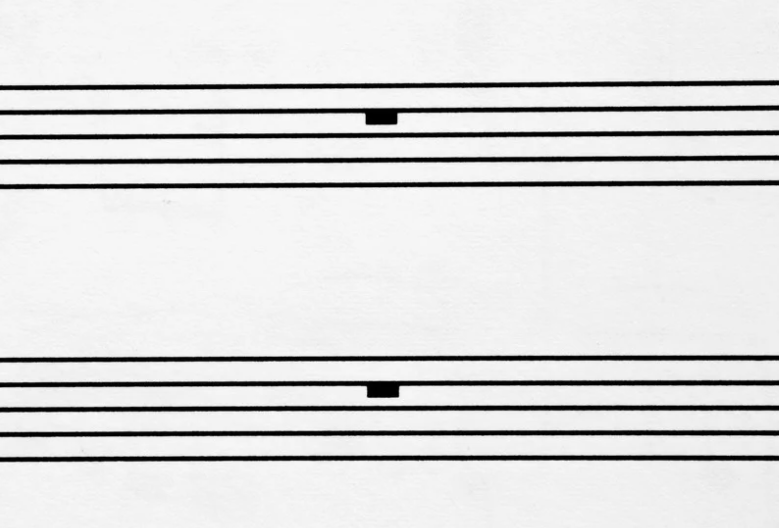
楽譜には、音を出さない時間を示す「休符」があります。四分休符なら四分音符分の休みを、二分休符なら二分音符分の休みを意味します。また、音符の右についた「・(付点)」は音を1.5倍に伸ばす記号です。さらに、音符同士を弧でつなぐ「タイ」は、2つの音をつなげて1つの音として演奏する指示になります。これらを正確に読むことで、リズムの表現が豊かになります。五線譜の読み方を理解すると、タブ譜だけでは表せない細かなニュアンスまで演奏できるようになります。
読譜練習で上達するためのステップ

ステップ1:弦と音名を覚える
ギターの読譜練習を始める前に、まず各弦の音名をしっかり覚えましょう。6弦から順にE(ミ)・A(ラ)・D(レ)・G(ソ)・B(シ)・E(ミ)です。この6本の弦の音を基準に、フレットを1つ進むごとに半音上がります。たとえば、5弦の開放弦Aから2フレットに移動すればBになります。音名を理解すると、譜面上の音を指板上で素早く探せるようになり、楽譜を読むスピードが格段に上がります。
ステップ2:簡単なフレーズを読んで弾く
初めて読譜練習を行う場合は、1弦だけを使ったメロディから始めるのがおすすめです。「ドレミファソラシド」などのシンプルなスケールをタブ譜で読み、指の位置と音の高さを一致させる練習を繰り返します。慣れてきたら、2本以上の弦を使った簡単なフレーズにも挑戦してみましょう。リズムを一定に保つことを意識しながら、メトロノームを使うとより効果的です。少しずつ読むスピードを上げていくことで、読譜力と演奏力の両方が自然に向上していきます。
ステップ3:複音・リズム譜の読譜練習
読譜に慣れてきたら、2つ以上の音を同時に鳴らす「複音」やリズム譜の練習に進みましょう。ギターでは、同じ音でもポジションが異なるため、どの位置で弾くかを自分で選ぶ力も求められます。譜面を見てすぐに指板上のポジションを判断できるようになると、演奏の自由度が広がります。また、ストロークやアルペジオなどのパターンを譜面で理解し、リズムを体で感じながら弾くことで、演奏全体に安定感が生まれます。
読譜力を伸ばすコツとおすすめ練習法
初見力(初めて見る譜面を読む力)を鍛える
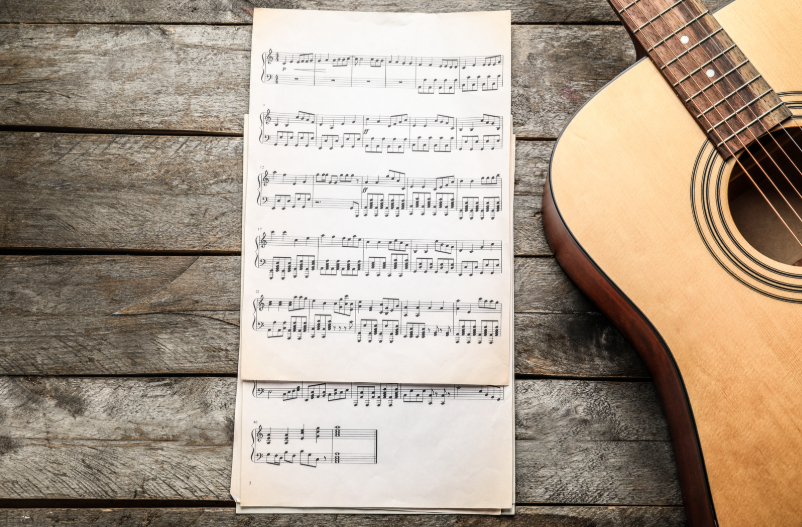
読譜力を高める上で欠かせないのが「初見練習」です。初めて見る譜面を一定のテンポで最後まで弾く練習を行うことで、目で見た情報を素早く音に変換する力が育ちます。最初は簡単なメロディ譜やタブ譜を使い、間違えても止まらず最後まで弾き切ることがポイントです。メトロノームを使いながら、少しずつテンポを上げていくと効果的です。初見力がつくと、新しい曲への対応力が上がり、バンド練習やセッションでも自信を持って演奏できるようになります。
実際の楽譜を使って練習する
市販のスコアやオンラインの楽譜サイトを活用して、実際の楽曲で練習するのもおすすめです。自分の好きなアーティストの曲や、簡単なポップス曲を題材に選ぶと、楽しく続けやすくなります。初めは1曲のサビ部分だけを練習しても構いません。譜面を読む力と同時に、コード進行やリズムパターンの理解も深まります。また、曲の中で登場する奏法記号を調べながら弾くことで、自然と楽譜記号の意味も身についていきます。

アプリや教材を活用する

スマホアプリやオンライン教材を使えば、効率的に読譜を学べます。「Yousician」や「MuseScore」などは、演奏に合わせて譜面がスクロールし、視覚的に音の位置を把握しやすいツールです。ゲーム感覚で練習できるアプリも多く、モチベーションを維持しながら継続的に学べます。また、紙の教材も併用すると、譜面を読む習慣がより強化されます。アプリと実際の譜面を組み合わせて学ぶことで、読譜スピードと理解力の両方を効果的に伸ばすことができます。
よくある質問(Q&A)
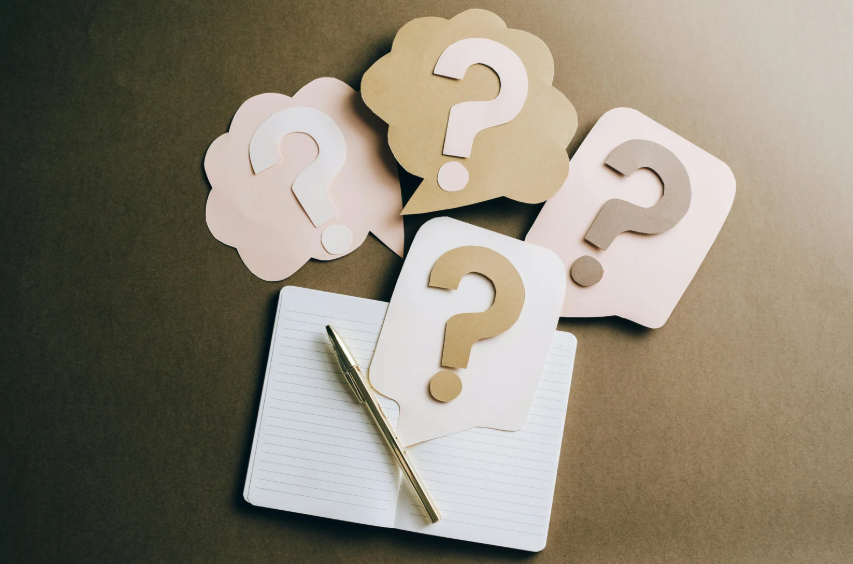
Q1:楽譜が全く読めません。どこから始めればいい?
まずはタブ譜から始めましょう。タブ譜はギター専用の楽譜で、数字を見てその通りに押さえるだけなので直感的に理解できます。最初は1弦だけのメロディや、単音で簡単なフレーズを弾く練習から始めると良いでしょう。
Q2:タブ譜だけではダメですか?
タブ譜だけでも演奏は可能ですが、リズムや表現力を磨くには五線譜の理解も必要です。タブ譜は押さえ方を示す便利なツールですが、音の長さや強弱までは正確に表せません。五線譜も少しずつ読めるようにしておくと、音楽的な幅が広がります。
Q3:コード譜と五線譜、どちらを優先すべき?
弾き語りや伴奏を楽しみたい方はコード譜、メロディを弾きたい方は五線譜を優先すると良いでしょう。どちらかに慣れてきたら、もう一方も並行して学ぶのが理想です。最終的には、曲に応じてどの譜面を使うか判断できるようになるのがベストです。
よくあるミスと注意点
・タブ譜だけに頼りすぎない
タブ譜は便利ですが、押さえる場所しかわからないため、音楽的な理解が浅くなりがちです。タブ譜を使いつつ、リズムや拍子も意識して弾くようにしましょう。
・表記の違いに注意する
出版社やアレンジによって、同じ曲でも記号や指示の表記が異なることがあります。「D.S.」「Fine」「Coda」などの反復記号の意味を理解しておくと、混乱せずに演奏できます。
・リズムを無視しない
音の長さやタイミングを正確に守ることは、演奏全体の完成度を大きく左右します。リズム譜を読む練習を繰り返し、メトロノームに合わせて弾く習慣をつけると安定した演奏ができるようになります。
まとめ

ギターの楽譜は一見複雑に見えますが、仕組みを理解すれば誰でも読めるようになります。
まずはタブ譜からスタートし、慣れてきたらコード譜や五線譜にも挑戦してみましょう。
楽譜が読めるようになると、曲の構造が理解でき、音楽の楽しみ方が何倍にも広がります。
日々の練習の中で「読む力」を意識しながらギターに触れることで、演奏の幅も表現力も格段に成長します。
アサヒ音楽教室の体験レッスンへ

アサヒ音楽教室では、ギター初心者の方でも安心して学べるよう、タブ譜やコード譜の読み方を基礎から丁寧に指導しています。経験豊富な講師があなたのペースに合わせてサポートし、「読める」「弾ける」「楽しめる」を実感できるレッスンを提供しています。体験レッスンは無料で受講可能です。楽譜が読めるようになりたい方、演奏の幅を広げたい方は、ぜひ一度体験レッスンにお申し込みください。あなたの音楽の第一歩を、アサヒ音楽教室が全力で応援します。
関連記事
-

2026年2月16日
講師ブログピアノ教室の体験レッスンは何を見る?後悔しないためのチェックポイントと失敗しない先生の選び方完全ガイド
ピアノ教室の体験レッスンへ行く前に知っておきたい基礎知識 ピアノ教室選びで「体験」が最も重要視される理由 ピアノという楽器は、他の習い事と比較しても講師と生徒が一対一で向き合う時間が非常に長いのが特徴...
-

2026年2月16日
講師ブログ楽器演奏は最高の「脳の筋トレ」!ストレス解消から認知症予防まで驚きの効果を徹底解説
音楽を趣味にするメリットとは?人生の質(QOL)が劇的に変わる理由 日々の仕事や家事に追われ、ふと「自分を豊かにする時間が足りない」と感じることはありませんか。ストレス社会と呼ばれる現代において、心の...
-

2026年2月16日
講師ブログ音楽教室の振替は無料が安心!後悔しない選び方と回数・期限・注意点を徹底解説【2026年最新ガイド】
急な予定変更や体調不良…月謝を無駄にしたくない方へ 音楽教室に通い始める際、多くの方が抱く不安の一つが「急な予定が入ったときにレッスンはどうなるのか」という点です。仕事での残業や急な出張、あるいは自分...
Blog 講師ブログ
-
2026年2月16日
音楽教室の振替は無料が安心!後悔しない選び方と回数・期限・注意点を徹底解説【2026年最新ガイド】
急な予定変更や体調不良…月謝を無駄にしたくない方へ 音楽教室に通い始める際、多くの方が抱く不安の一つが「急な予定が入ったときにレッスンはどうなるのか」という点です。仕事での残業や急な出張、あるい...
-
2026年2月16日
ピアノ教室の体験レッスンは何を見る?後悔しないためのチェックポイントと失敗しない先生の選び方完全ガイド
ピアノ教室の体験レッスンへ行く前に知っておきたい基礎知識 ピアノ教室選びで「体験」が最も重要視される理由 ピアノという楽器は、他の習い事と比較しても講師と生徒が一対一で向き...
-
2026年2月16日
楽器演奏は最高の「脳の筋トレ」!ストレス解消から認知症予防まで驚きの効果を徹底解説
音楽を趣味にするメリットとは?人生の質(QOL)が劇的に変わる理由 日々の仕事や家事に追われ、ふと「自分を豊かにする時間が足りない」と感じることはありませんか。ストレス社会と呼ばれる現代...
Course コース一覧
Area スタジオエリア一覧
| 東京23区 |
|---|
| 東京23区外 |
|---|
| 神奈川県 |
|---|
| 千葉県 |
|---|
| 埼玉県 |
|---|


