Blog 講師ブログ
2025年10月1日
トロンボーン初心者完全ガイド|効果的な練習法

トロンボーン初心者が知っておくべき基本
トロンボーンの魅力と役割
「トロンボーンに挑戦してみたいけれど、どんな楽器を選べばいいのか分からない…」「練習の仕方が分からず、始める前から不安になってしまう」──そんな気持ちを抱いている方も多いのではないでしょうか。
トロンボーンは、金管楽器の中でも特に初心者から人気のある楽器です。重厚であたたかみのある音色を出せる一方、スライド操作がユニークで、最初は戸惑う人も少なくありません。でも大丈夫。選び方のポイントや、初めての練習で意識すべきことを押さえれば、着実に上達していけます。
このページでは、これからトロンボーンを始めたい初心者の方に向けて、
最初の1本はどんな楽器を選べば安心か.
基礎練習はどんなステップから取り組めばよいか
吹奏楽やジャズでどんな楽しみ方ができるか
を分かりやすく紹介していきます。
吹奏楽・ジャズ・クラシックでの位置づけ

吹奏楽でのトロンボーンは、サウンド全体を支える中低音セクションの柱です。クラシックでは交響曲や協奏曲の中で荘厳な響きを担当し、時にソロで観客を魅了します。ジャズにおいてはグリッサンドや豊かな表現力を活かして即興演奏の花形となります。
初心者が最初にトロンボーンを学ぶ際は、それぞれのジャンルでの役割を理解しておくと、練習の目的や音色作りに意識を向けやすくなります。
初心者が最初に押さえるべき流れ
トロンボーン初心者は、 ひとつずつ基本を押さえながら練習を行うことが重要です。
上達までの流れ
1)正しい姿勢・構え方を覚える
2)呼吸法やマウスピースでのバズィングで音を安定させる
3)ロングトーンで音程を安定させる
4)スライド操作の基本を学びポジションを覚える
5)簡単な曲に挑戦しながらモチベーションを維持
練習の順序を理解することで、効率よく上達することが可能になります。
トロンボーンの種類と選び方

テナー/テナーバス/アルト/バスの違い
初心者が手にすることが多いのはテナートロンボーンです。最も標準的で扱いやすく、吹奏楽やジャズの入門に適しています。テナーバストロンボーンはF管が付属し、低音域を補強できます。アルトトロンボーンは小型で高音域向き、バストロンボーンは大型で重厚な低音が魅力です。
初心者には、まずテナーかテナーバスが推奨されることが多く、自身の演奏目的や体格に応じて選ぶと良いでしょう。
太管・細管の特徴と初心者のおすすめ
トロンボーンには「太管(ラージボア)」と「細管(スモールボア)」があります。太管は豊かな音量が得られ、吹奏楽やクラシックで力強い響きを作るのに適しています。一方、細管は軽快で明るい音色を出しやすく、ジャズやポップスに向いています。
初心者が最初に選ぶ場合は、吹奏楽部やオーケストラで使用するなら太管、軽やかな演奏を楽しみたいなら細管が選びやすいです。目的に応じた選択が上達への近道です。
楽器購入の予算と中古選びのポイント
初心者がトロンボーンを購入する際の予算は、エントリーモデルなら5万円から10万円前後が目安です。新品を選べば保証や安心感がありますが、中古でも状態が良ければ十分に活用できます。
中古品を購入する際は、スライドの動きがスムーズか、ベルに大きなへこみがないかを確認しましょう。信頼できる楽器店で調整済みの中古を選ぶと、コストを抑えつつ安心して演奏を始められます。
マウスピース選びの基本
マウスピースはトロンボーン初心者にとって音の出しやすさを左右する重要な要素です。リムのサイズやカップの深さによって吹奏感や音色が変わります。標準的なサイズを選ぶことで、無理なく音を出すことができます。深いカップは柔らかい音を出しやすく、浅いカップは明るい音が得られます。初心者のうちは、楽器店や先生のアドバイスを受けながら標準モデルを選ぶとよいでしょう。
正しい構え方と持ち方

立奏・座奏の基本姿勢
初心者がトロンボーンを演奏するときにまず意識すべきは姿勢です。立奏の場合は背筋をまっすぐに保ち、肩の力を抜いて自然に構えます。座奏では椅子に深く座らず、背筋を伸ばして骨盤を立てることがポイントです。どちらの場合も息の通り道を確保するために、胸を開いて呼吸しやすい姿勢を心がけましょう。正しい姿勢は音の響きを大きく改善し、初心者の成長を助けてくれます。
左手の保持と右手スライドの使い方
トロンボーンは左手で楽器を支え、右手でスライドを操作します。左手はスライドの根本を安定して保持し、手首や腕に無理な力を入れないことが大切です。右手は親指と二本の指でスライドを軽くつかみ、スムーズに動かせるようにします。初心者は力を入れすぎてしまいがちですが、柔らかく持つことで動作がスムーズになり、安定した演奏につながります。
音を出すための準備

呼吸法と腹式呼吸の意識
トロンボーン初心者にとって、安定した音を出すためには呼吸法が欠かせません。特に腹式呼吸を意識することで、長く途切れない息を楽器に送り込めます。お腹を膨らませるように吸い、吐くときはゆっくりと支えるように息を流します。胸だけで呼吸してしまうとすぐに息切れし、音がかすれてしまいます。基礎の呼吸練習を繰り返すことで、演奏の土台がしっかりと築かれます。
マウスピースバズィングの練習
初心者が最初に取り組むべきトレーニングが「マウスピースバズィング」です。マウスピースだけを使って唇を振動させ、安定した音を出す練習です。最初は短い時間で構わないので、安定して同じ音を出せるよう繰り返しましょう。バズィングによって唇の筋肉が鍛えられ、音程をコントロールする力がついていきます。楽器を装着する前に行うことで、音の出だしがスムーズになります。
息のスピードと量のコントロール
音を出す際には、息の「量」と「スピード」が重要です。初心者は息を強く吹き込みすぎる傾向がありますが、必要以上に力を入れると音が荒れてしまいます。大切なのは息を安定して一定に流すことです。低音は多めの息を、ややゆっくりと。高音はスピードを意識し、細い息を流すときれいに響きます。呼吸をコントロールできるようになると、安定した音作りにつながります。
ロングトーンで音を育てる

ロングトーンの目的と効果
ロングトーンとは、一つの音を長く伸ばす練習のことです。トロンボーン初心者にとっては音程の安定や音色の改善に直結する重要な基礎練習です。息の流れを一定に保ちながら演奏することで、肺活量や持久力も自然に鍛えられます。毎日の練習に取り入れることで、楽器をしっかり鳴らす感覚が身につきます。地道ですが確実に上達を感じられるメニューです。
音程・音色・持久力の安定
ロングトーンを続けることで、音程のブレを抑えられるようになります。トロンボーンはスライド楽器のため、音程を耳で正しく判断する力が不可欠です。また、同じ音を安定して伸ばす過程で唇の持久力が養われ、長時間の演奏にも対応できるようになります。音色のムラがなくなり、豊かで美しい響きが得られるのもロングトーンの効果です。
チューナーやドローン音源を使った練習
初心者がロングトーン練習をする際は、チューナーやドローン音源を活用すると効果的です。チューナーで音程を確認することで、自分の音のズレを客観的に把握できます。また、ドローン音源(一定の音を流し続ける音源)に合わせて練習すると、耳でハーモニーを感じながら正しい音程を身につけられます。こうした補助ツールを使うことで、効率的に音程感覚を養えます。
スライドの基本をマスター

7つのポジションと覚え方
トロンボーンには7つのスライドポジションがあり、それぞれの位置で異なる音を出します。初心者にとっては距離感を覚えるのが難しいですが、まずは第1ポジション(スライドを完全に引き込んだ位置)から始めましょう。少しずつ腕を伸ばして2〜7ポジションを確認し、耳で音程を覚えていきます。目安を知りつつ、最終的には耳で正確に合わせることが重要です。
目印に頼らない耳での確認
スライドにはポジションの「目安」がありますが、実際の音程は演奏環境や個人の体格によって微妙に変化します。そのため、初心者は目で見るより耳で聴くことを優先する必要があります。チューナーを使って位置を確認しながら、音を聴いて合わせる練習をしましょう。耳を使う習慣を身につけると、アンサンブルでも正しい音程感を保てるようになります。
半音・全音移動の基礎ドリル
初心者がスライドを練習する際には、半音移動と全音移動の反復練習が効果的です。例えば1→2ポジションの移動をゆっくり繰り返し、音程を確認しながら滑らかに動かせるようにします。慣れてきたらメトロノームを使ってテンポを上げ、正確にポジションへ到達する練習を重ねましょう。こうした基礎ドリルは、楽曲を吹く際の安定した演奏につながります。
よくあるスライドの失敗と修正法
トロンボーン初心者がよく陥る失敗は、スライドを速く動かしすぎて音が雑になることです。また、ポジションに届かず音程が高くなったり、逆に伸ばしすぎて低くなったりすることもあります。修正法としては、ゆっくりとしたテンポで確実にポジションに到達する練習を繰り返すことです。肩や腕の力を抜き、自然にスライドを動かす意識を持つと改善されます。
初心者の練習ロードマップ
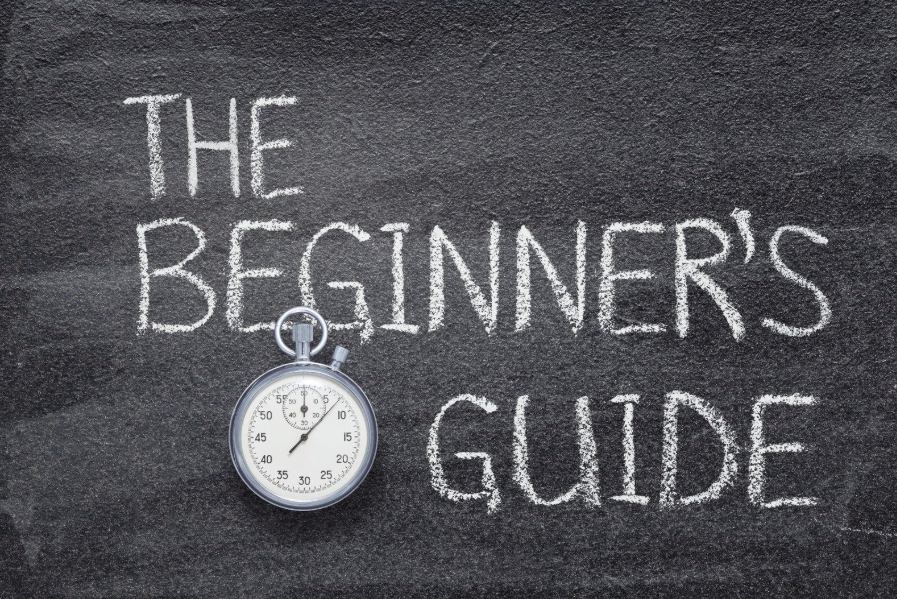
初めの1か月(呼吸・バズィング・ロングトーン)
トロンボーン初心者は、まず楽器に慣れる期間を大切にしましょう。最初の1か月は呼吸法やマウスピースバズィング、ロングトーンに重点を置きます。短い時間でも構いませんが、毎日継続することが重要です。簡単な音階を試しながら、楽器の仕組みやスライドの感覚を体に覚え込ませていきます。焦らず基礎を固めることで、後の上達が格段にスムーズになります。
1〜3か月(スライド精度・短い曲への挑戦)
基礎が身についたら、1〜3か月目ではスライド精度を高める練習に移行します。半音や全音の移動練習を繰り返しながら、ポジションの感覚を磨きます。また、簡単な童謡や短いメロディに挑戦することで、練習に楽しさが加わります。録音をして自分の音程やリズムを客観的に確認するのも有効です。小さな成功体験が積み重なることで、練習のモチベーションが持続します。
3〜6か月(音域拡張とアンサンブル参加)
3か月を過ぎた頃からは、徐々に音域を広げる練習を取り入れていきましょう。低音から高音までの幅を広げることで、演奏できる曲が格段に増えます。持久力をつけるために、長めのフレーズを通して吹く練習も大切です。また、可能であれば合奏やアンサンブルに参加することで、音程やリズム感が飛躍的に向上します。仲間と音を合わせる楽しさは、継続の大きな原動力になります。
練習時間別メニュー(15分/30分/60分)
初心者は毎日の練習を習慣化することが大切です。時間が少ないときは15分だけでも、呼吸・バズィング・ロングトーンを行いましょう。30分確保できる場合は、加えてスライド練習や短い曲を取り入れると効果的です。60分あるときは、基礎練習に加えて曲の仕上げやアンサンブル練習を行うと充実します。時間に応じたメニューを組むことで、無理なく継続できます。
初心者におすすめの練習曲・定番曲

簡単に吹ける童謡や賛美歌
トロンボーン初心者に最適な練習曲として、音域が狭くシンプルな旋律の童謡や賛美歌があります。「きらきら星」や「きよしこの夜」は、音の跳躍が少なく安定した音程練習に適しています。これらの曲は耳なじみがあり、音程やリズムを確認しながら楽しく練習できます。初心者が基礎を固めながら音楽の楽しさを感じるために、こうしたやさしいメロディから取り組むのがおすすめです。
ポップスや映画音楽で楽しく練習
基礎練習に慣れてきたら、映画音楽やポップスに挑戦すると楽しさが増します。「アメイジング・グレイス」や「パイレーツ・オブ・カリビアン」のテーマ曲は、初心者でも比較的吹きやすいアレンジが多く、市販の楽譜も豊富です。身近なメロディを演奏することでモチベーションが上がり、練習を継続しやすくなります。基礎力を活かして少しずつ表現力を磨いていきましょう。
少し背伸びできる吹奏楽・ジャズ曲
初心者が次のステップとして挑戦しやすいのが、シンプルな吹奏楽曲やジャズのスタンダードです。吹奏楽曲なら「アルセナール」などの有名なマーチ、ジャズでは「When the Saints Go Marching In」が手軽です。こうした楽曲は合奏にもよく登場するため、練習しておくと今後の演奏活動にも役立ちます。やや難しさがある分、吹けるようになった時の達成感も大きいでしょう。
曲を仕上げるためのチェックリスト
初心者が一曲を仕上げる際には、以下のポイントを確認しましょう。
・音程が安定しているか
・リズムが正確か
・フレーズ感が滑らかかどうか
・ブレス位置が自然か
録音して客観的に聴くと、自分の弱点を見つけやすくなります。仕上げの段階では、単に音を出すだけでなく「曲として表現できているか」を意識することが大切です。
初心者がつまずくポイントと解決策

音が出ない/続かないとき
トロンボーン初心者が最初に直面する悩みの一つが「音が出ない、または続かない」という問題です。これは息のスピードや唇の閉じ方が不安定なことが原因です。解決策としては、短時間のマウスピースバズィングから始め、息を安定させる練習を繰り返すことです。腹式呼吸を意識し、息を強く吹くよりも一定に流すことを優先すると改善されます。
高音が出しづらいとき
初心者が高音を出そうとすると、つい力任せになってしまいがちです。しかし力を入れすぎると逆に唇が固まり、きれいな音が出なくなります。高音を出すコツは、息のスピードを速めることと、口角をやや引き締めて唇の振動を細かくすることです。無理に高音を出そうとせず、少しずつ音域を広げる練習を重ねると安定して高音が出せるようになります。
音程が不安定なとき
スライド楽器であるトロンボーンは、音程の不安定さに悩む初心者が多いです。音程を安定させるためには、ロングトーン練習とチューナーを使った確認が効果的です。また、ドローン音源に合わせて演奏し、耳で正しい音程を感じることも大切です。スライドの微調整は時間がかかりますが、耳を育てながら繰り返し練習すれば確実に改善していきます。
スライドが間に合わないとき
テンポの速い曲や音程移動の大きいフレーズでは、スライド操作が間に合わないと感じることがあります。初心者はつい力んでしまい、逆に動作が遅くなりがちです。肩の力を抜き、腕を自然に伸ばすイメージで練習するとスライドが滑らかに動きます。まずはゆっくりしたテンポで正確にポジションへ到達する練習を重ね、徐々にスピードを上げていくのが効果的です。
音が汚れてしまうとき
「音がザラつく」「濁ってしまう」というのもトロンボーン初心者のよくある悩みです。これは唇の振動が不安定だったり、息の流れが途切れたりしている場合に起こります。改善するには、まず息の支えをしっかり意識し、力まずに吹くことが大切です。ロングトーンや短いフレーズの繰り返しで、安定した音の基礎を作ることが解決の近道になります。
基本テクニックを身につける
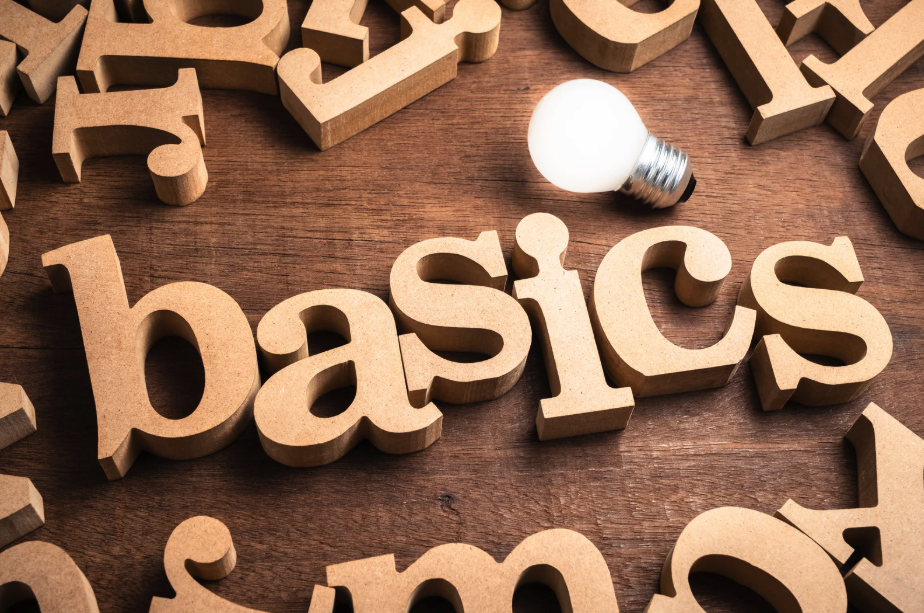
タンギングの基本
トロンボーン初心者が早い段階で習得すべきなのがタンギングです。舌で息の流れを区切り、音の出だしを明確にします。最初は「タッ」「ダッ」といった軽い発音を意識し、ゆっくり練習しましょう。舌を強く当てすぎると音が硬くなるので、息の流れを優先しながら自然に区切ることが大切です。タンギングを覚えると、リズム感がつき演奏の表現力が大きく広がります。
リップスラーで倍音を使いこなす
リップスラーとは、スライドを動かさず唇の振動を変えて倍音を切り替える練習です。初心者にとっては難しく感じますが、音域を広げるために欠かせません。低音から高音へ、またその逆へとゆっくり練習し、徐々にスムーズに移動できるようにしましょう。リップスラーは唇と息のコントロールを磨く基礎であり、上達に直結する重要なテクニックです。
グリッサンドの表現と注意点
トロンボーンならではの表現に「グリッサンド」があります。スライドを滑らかに動かすことで、音と音の間を連続的につなげる奏法です。ジャズやポップスでは効果的に使うことで演奏にアクセントを加えられます。ただし、使いすぎると冗長に聞こえるため、場面を選んで活用することが大切です。初心者はまず短い音程間で試し、少しずつ表現力を磨いていきましょう。
ダイナミクスの練習法
音の強弱(ダイナミクス)は音楽表現を豊かにする要素です。初心者は「大きく吹く=力を入れる」と考えがちですが、実際は息のスピードと量のコントロールで調整します。小さな音では息を細く安定して流し、大きな音ではしっかり支えを意識しながら吹きます。ロングトーンに強弱を加えて練習することで、自然にダイナミクスを操れるようになります。
トロンボーンのメンテナンス

スライドクリーム・オイルの使い方
トロンボーン初心者が必ず覚えるべきなのが、スライドのメンテナンスです。スライドは常に滑らかに動く必要があり、専用のクリームやオイルを適量塗布して使います。オイル使用後に水をスプレーすることで、より軽やかに動かせます。手入れを怠ると動きが悪くなり、演奏に支障をきたします。定期的なメンテナンスは、快適な演奏環境を保つために不可欠です。
管内クリーニングの頻度と方法
管内の掃除も初心者が早めに習慣化すべきお手入れです。長期間放置すると唾液や汚れが溜まり、音の響きが悪くなるだけでなく衛生面にも問題が生じます。練習の度に掃除用のスワブやブラシを使い、週に一度程度は管の内部を洗浄するとよいでしょう。定期的に管内を清潔に保つことで、快適な音色を長く維持できます。
マウスピース洗浄と保管
マウスピースは口に直接触れる部分のため、初心者でも毎日清潔に保つことが大切です。使用後は水で洗い、必要に応じて専用ブラシで内部を磨きます。乾燥させてからケースに収納することで、錆や劣化を防げます。小さなケアですが、音の出しやすさや衛生面に直結するため、欠かさず行う習慣を身につけましょう。
ケース選びと持ち運びの注意
楽器を守るためにはケース選びも重要です。初心者は軽量で持ち運びやすいソフトケースを選びがちですが、保護性を考えるとハードケースの方が安心です。移動中は必ずスライドロックを確認し、無理な衝撃を与えないように注意しましょう。ケースの選び方ひとつで楽器の寿命が大きく変わるため、慎重に選ぶことをおすすめします。
合奏に参加する前に知っておきたいこと

チューニングと音程合わせ
合奏に参加する際、初心者がまず意識すべきはチューニングです。基準音に合わせて楽器の全体的な音程を整えることが大切です。トロンボーンはスライド操作によって微調整できるため、耳を使って常に音を合わせる習慣をつけましょう。正しいチューニングができると合奏全体の響きが安定し、仲間との一体感も得られます。
パート内での役割(ハーモニーの支え方)
トロンボーンは合奏で中低音を担い、ハーモニーの土台を支える役割があります。初心者でも音程をしっかり合わせ、一定のリズムで安定した音を出すことを意識しましょう。メロディを演奏することもありますが、多くは他の楽器を引き立てる伴奏的な役割です。自分の音が全体の中でどのように響いているかを聴く耳を持つことが重要です。
指揮者やパートリーダーとの連携
合奏では、個人練習とは異なり指揮者やパートリーダーとの連携が必要になります。演奏中は常に指揮を見てテンポを合わせ、リーダーの指示に耳を傾けましょう。初心者でも積極的に周囲の音を聴き、他のパートとのバランスを意識することで、より良い合奏が生まれます。協調性を持って参加する姿勢が、上達と信頼につながります。
練習を続けるコツとモチベーション維持

練習ログと録音の活用
トロンボーン初心者が上達を実感するには、自分の練習を記録することが効果的です。毎日の練習内容や時間をログに残すと、積み重ねが見えるためモチベーションが上がります。また、録音して自分の音を客観的に聴くことで、改善点が明確になります。自分では気づきにくいリズムのズレや音程のブレも、録音なら一目瞭然です。練習記録を習慣化することで、効率的に成長できます。
小目標を設定して達成感を得る
大きな目標だけを掲げていると、初心者は途中で挫折しやすくなります。そこで「今日はロングトーンを5分続ける」「このフレーズを滑らかに吹けるようにする」といった小さな目標を設定するとよいでしょう。短期間で達成感を得られるため、モチベーションの維持につながります。小目標を積み重ねることで、自信が育ち、自然と大きなステップアップへと進めます。
独学とレッスンのバランス
トロンボーンは独学でもある程度の基礎を身につけられますが、どうしても癖がつきやすい楽器です。初心者は定期的に先生や経験者からフィードバックを受けると、無駄な遠回りをせずに済みます。独学で自主的に練習しつつ、レッスンで正しいフォームや音の出し方を確認するのがおすすめです。このバランスが取れると、効率よく上達できます。
オンラインレッスンや教材の活用
最近はオンラインレッスンや動画教材も充実しており、初心者でも手軽に学べる環境が整っています。移動の手間がなく、自宅で先生から直接指導を受けられるのは大きなメリットです。また、動画教材なら繰り返し視聴できるため、基礎を確実に理解できます。自分の生活リズムに合った学び方を取り入れることで、継続しやすくなります。
耳を育てる鑑賞ガイド

クラシックの名曲で学ぶ
クラシック音楽はトロンボーンの魅力を存分に味わえるジャンルです。初心者には、ベートーヴェンの交響曲第5番やマーラーの交響曲が特におすすめです。壮大で重厚な響きの中で、トロンボーンがどのように役割を果たしているかを聴き取ることで、自分の演奏に活かせます。耳を育てることは、音程感や表現力を磨く近道です。
ジャズやビッグバンドの聴きどころ
ジャズやビッグバンドにおけるトロンボーンは、ソロやセクションプレイで大活躍します。グレン・ミラーやカウント・ベイシー楽団の演奏を聴くと、スイング感やグリッサンドの使い方がよくわかります。初心者でもジャズ特有のリズムやノリを感じることで、演奏の幅が広がります。多様な音楽に触れることが、練習のモチベーションにもつながります。
おすすめの演奏家と録音
世界的に有名なトロンボーン奏者の演奏を聴くことも、初心者には大きな学びとなります。クラシックならクリスチャン・リンドベルイ、ジャズならJ.J.ジョンソンやカーティス・フラーなどが代表的です。プロの演奏を繰り返し聴くことで、音色の美しさや表現力の幅を実感できます。憧れの演奏家を持つことは、練習の大きな励みになります。
プレイリストの作り方
初心者が効率よく耳を育てるためには、自分専用のプレイリストを作るのがおすすめです。クラシック、ジャズ、映画音楽などジャンルごとにまとめると比較しやすくなります。毎日少しずつでも聴き続けることで、自然と音程感やリズム感が磨かれていきます。鑑賞を練習と同じくらい大切にすることで、演奏の質が大きく向上します。
まとめと次のステップ

半年間の到達目標
トロンボーン初心者が半年間しっかり練習すると、基礎的な音の出し方やロングトーン、簡単な曲を演奏できるようになります。スライド操作にも慣れ、音域も広がり始めるでしょう。自分の成長を感じられる時期なので、継続する意欲も高まります。半年を一区切りとし、到達度を自己評価することが次のステップにつながります。
上達度チェックのポイント
上達を確認するためには、以下ののチェック項目があります。
・安定した音が出せるか
・音程が正確か
・リズムを守れているか
・曲を最後まで通して演奏できるか
安定した音が出せるか、音程が正確か、リズムを守れているか、そして曲を最後まで通して演奏できるかです。録音や先生のフィードバックを参考に、自分の成長を客観的に把握しましょう。こうしたチェックはモチベーション維持にも効果的です。
次の練習テーマと発表会準備
半年を過ぎたら、新しい練習テーマに挑戦するのもおすすめです。例えば、高音域や低音域の拡張、複雑なリズムへの対応などです。また、発表会や人前での演奏を目標にすると、練習に具体的な目的が生まれます。初心者でも発表会を経験することで、演奏の自信がつき、さらに上達のきっかけとなります。
トロンボーンを楽しみ続けるために
最も大切なのは「楽しみながら続けること」です。トロンボーンは習得に時間がかかりますが、練習を重ねるごとに確実に成長を感じられる楽器です。仲間と合奏したり、好きな曲を演奏したりすることで、日々の練習が充実します。初心者でも一歩ずつ進めば、豊かな音楽体験を長く楽しめるでしょう。
関連記事
-

2026年2月16日
講師ブログピアノ教室の体験レッスンは何を見る?後悔しないためのチェックポイントと失敗しない先生の選び方完全ガイド
ピアノ教室の体験レッスンへ行く前に知っておきたい基礎知識 ピアノ教室選びで「体験」が最も重要視される理由 ピアノという楽器は、他の習い事と比較しても講師と生徒が一対一で向き合う時間が非常に長いのが特徴...
-

2026年2月16日
講師ブログ楽器演奏は最高の「脳の筋トレ」!ストレス解消から認知症予防まで驚きの効果を徹底解説
音楽を趣味にするメリットとは?人生の質(QOL)が劇的に変わる理由 日々の仕事や家事に追われ、ふと「自分を豊かにする時間が足りない」と感じることはありませんか。ストレス社会と呼ばれる現代において、心の...
-

2026年2月16日
講師ブログ音楽教室の振替は無料が安心!後悔しない選び方と回数・期限・注意点を徹底解説【2026年最新ガイド】
急な予定変更や体調不良…月謝を無駄にしたくない方へ 音楽教室に通い始める際、多くの方が抱く不安の一つが「急な予定が入ったときにレッスンはどうなるのか」という点です。仕事での残業や急な出張、あるいは自分...
Blog 講師ブログ
-
2026年2月16日
音楽教室の振替は無料が安心!後悔しない選び方と回数・期限・注意点を徹底解説【2026年最新ガイド】
急な予定変更や体調不良…月謝を無駄にしたくない方へ 音楽教室に通い始める際、多くの方が抱く不安の一つが「急な予定が入ったときにレッスンはどうなるのか」という点です。仕事での残業や急な出張、あるい...
-
2026年2月16日
ピアノ教室の体験レッスンは何を見る?後悔しないためのチェックポイントと失敗しない先生の選び方完全ガイド
ピアノ教室の体験レッスンへ行く前に知っておきたい基礎知識 ピアノ教室選びで「体験」が最も重要視される理由 ピアノという楽器は、他の習い事と比較しても講師と生徒が一対一で向き...
-
2026年2月16日
楽器演奏は最高の「脳の筋トレ」!ストレス解消から認知症予防まで驚きの効果を徹底解説
音楽を趣味にするメリットとは?人生の質(QOL)が劇的に変わる理由 日々の仕事や家事に追われ、ふと「自分を豊かにする時間が足りない」と感じることはありませんか。ストレス社会と呼ばれる現代...
Course コース一覧
Area スタジオエリア一覧
| 東京23区 |
|---|
| 東京23区外 |
|---|
| 神奈川県 |
|---|
| 千葉県 |
|---|
| 埼玉県 |
|---|


