Blog 講師ブログ
2025年9月12日
DTM初心者完全ガイド|機材選びと作曲入門

導入:DTM初心者が「最初の1曲」を作るために
DTM(デスクトップ・ミュージック)は、今や誰でも自宅で楽曲制作ができる時代の代名詞です。しかし「DTMを始めたいけれど、どんな機材が必要なのか」「そもそもどのソフトを使えば良いのか」と迷う方は多いでしょう。
本記事では、DTM初心者が最初の1曲を完成させるまでに必要な知識と流れを丁寧に解説します。読後には、自分の手で音楽を形にする第一歩を踏み出せるようになるはずです。
DTMとは?初心者が最初に理解すべき基礎知識

DTMとDAWの違い
DTMは「デスクトップ・ミュージック」の略称で、パソコンを使った音楽制作全般を指します。一方でDAW(Digital Audio Workstation)は、その中心となるソフトウェアのことです。
DTMという広い概念の中に、DAWという道具が含まれるイメージを持つとわかりやすいでしょう。CubaseやLogic、FL Studioなどは代表的なDAWで、録音・編集・打ち込み・ミックスなどすべての作業を行えます。
よく使う音楽用語の整理(MIDI・オーディオ・プラグインなど)
DTM初心者が混乱しやすいのが専門用語です。MIDIとは音符や演奏情報をデータとして扱う仕組みで、ピアノロールに入力して演奏を再現します。オーディオは実際の音声波形を録音したものです。
また、プラグインとはDAWに機能を追加するソフトで、エフェクトや音源として使います。これらの用語を理解しておくと、解説書や動画が格段に読みやすくなります。
なぜ今DTMが人気なのか(配信文化・動画投稿・AI音楽)
近年DTMが注目される理由は、音楽配信や動画投稿の普及にあります。YouTubeやTikTokでは個人が作った楽曲を発表し、多くのリスナーに届く時代です。
さらに、AI音楽やボカロの進化により、一人でも作品を完成させやすくなりました。バンドメンバーがいなくてもDTMならドラム、ベース、シンセまで揃い、オリジナル曲を形にできます。創作の自由度が高いことが、DTM人気の大きな要因です。
DTM初心者が揃えるべき最低限の機材

パソコンの推奨スペック(CPU・メモリ・SSD)
DTMを始めるにはまずパソコンが必要です。最低でもメモリ8GB、CPUはi5クラス以上、SSDのストレージを推奨します。
DTMは音源やプラグインを同時に動かすため処理負荷が高く、余裕のある性能を選ぶほど快適に制作できます。特にSSDはデータ読み込みが速いため、ソフト音源のロード時間を短縮でき、作業のストレスを軽減します。
DAWソフトの選び方(GarageBand/Logic/Cubase/FL Studioなど)
DTMの中心となるDAWは、音楽制作のスタイルに合わせて選ぶのが基本です。Macなら無料のGarageBandから始められ、上位版のLogicはプロでも愛用されています。
Cubaseは作曲・録音・編曲に万能で、国内外のユーザーも多く安心感があります。FL StudioはEDMやビートメイクに強く、直感的な操作性が魅力です。それぞれのDAWには体験版があるため、実際に触ってみて自分に合うものを選びましょう。
オーディオインターフェースとは?役割と選び方
楽器やマイクを録音する際に欠かせないのがオーディオインターフェースです。これはパソコンと外部機材を繋ぎ、高音質で録音や再生を可能にする機材です。
初心者向けには入力2ch、出力2chのシンプルなモデルで十分です。FocusriteやSteinbergなど信頼性の高いブランドがおすすめです。ASIOドライバ対応でレイテンシを抑えられるかどうかもチェックポイントになります。
ヘッドホン・モニタースピーカー・MIDIキーボード
制作に必須なのがモニタリング環境です。一般的なイヤホンやスピーカーでは音の再現性が低く、楽曲の仕上がりに影響します。そのためフラットな音質を持つモニターヘッドホンを導入しましょう。
モニタースピーカーは部屋の環境を整える必要があるため後からでも大丈夫です。MIDIキーボードは打ち込みを直感的に行うために便利で、鍵盤の有無が制作効率を大きく変えます。
予算別スターターセット例(3万円・5万円・10万円)
DTM初心者は予算に応じて機材を選ぶのがおすすめです。3万円ならパソコンと無料DAW、ヘッドホンだけで始められます。
5万円ならオーディオインターフェースやMIDIキーボードを追加でき、録音や演奏が可能になります。10万円あればモニタースピーカーや有料プラグインも導入でき、より本格的な環境で制作が可能です。段階的に揃えることで無理なくステップアップできます。
DAWソフトの特徴と選び方ガイド

GarageBand/Logic(Macユーザー向け)
Macユーザーにとって最初の一歩はGarageBandです。無料ながらも基本的な録音や打ち込み機能が揃っており、初心者には十分な環境です。さらに本格的に学ぶなら上位版のLogic Proを選びましょう。
豊富な音源やエフェクトが標準搭載され、ポップスから映画音楽まで幅広いジャンルに対応します。操作性も直感的で、世界中のクリエイターが使用しています。
Studio One(初心者向けシンプル設計)
Studio OneはシンプルなUIで直感的に操作できるDAWです。ドラッグ&ドロップ中心の設計は初心者にも扱いやすく、学習コストが低いのが特徴です。
音質や安定性にも定評があり、国内外で利用者が増えています。無料版のPrimeから始め、必要に応じてArtistやProfessionalにアップグレードできるため、長期的に使えるソフトです。
Cubase(王道・多機能)
Cubaseは世界中の作曲家やエンジニアが愛用する定番DAWです。MIDI編集の自由度が高く、オーケストラからバンド、EDMまで幅広く対応できます。
特にコードトラック機能やスコア編集機能は作曲支援として優秀で、音楽理論を学びながら制作できます。初心者からプロまでステップアップできる点も魅力で、DTMの王道ソフトと呼ばれる所以です。
FL Studio(EDMやビートメイクに人気)
FL StudioはEDMやヒップホップのトラックメイカーに絶大な人気を誇るDAWです。パターンベースの打ち込みが得意で、短時間でリズムやループを組み立てられます。
豊富な内蔵音源とエフェクトも魅力で、クラブミュージックを作りたい初心者には最適です。直感的な操作性に加え、終身無料アップデート制度があるため長く使い続けられるのも大きなメリットです。
Ableton Live(ライブパフォーマンス・エレクトロ系)
Ableton Liveはライブ演奏や即興制作に強いDAWです。セッションビューを活用すれば、ループを組み合わせてリアルタイムに曲展開を試せます。
エレクトロニカや実験的な音楽に向いており、ライブパフォーマンスを意識する人には特におすすめです。エフェクトや音源も実践的で、ステージと制作をシームレスに繋げられるのが最大の特徴です。
Pro Tools(プロスタジオ標準)
Pro Toolsは世界のプロフェッショナルスタジオで標準的に使われるDAWです。特に録音・編集機能に優れ、大規模なセッションや映画音楽、ナレーション制作に適しています。
操作にはある程度の慣れが必要ですが、業界標準を学ぶことは将来的な強みになります。初心者が自宅で使うにはやや敷居が高いですが、将来プロの現場を目指すなら検討に値する選択肢です。
1曲を完成させるまでの流れ(ロードマップ)

リファレンス曲を決める:模倣から学ぶ
DTM初心者にとって大切なのは、まず目標となるリファレンス曲を選ぶことです。好きなアーティストの楽曲や作りたいジャンルの代表曲を参考にしましょう。
テンポやキー、構成を分析し、それを手本として打ち込みやアレンジを進めると効率的です。模倣から入ることで、自然とジャンル特有のアレンジや音作りを吸収できます。
ドラムの打ち込み:リズムの基礎
DTM初心者にとって最初に挑戦するのはドラム打ち込みです。キック、スネア、ハイハットの3要素だけでシンプルなビートを作りましょう。まずは4つ打ちや8ビートから始めるのがおすすめです。
慣れてきたらフィルインや強弱を加えるとより自然に聴こえます。ドラムは楽曲の土台なので、シンプルかつ安定感を意識することが重要です。
ベースラインでグルーヴを作る
次に加えるのがベースです。ベースはリズムとハーモニーを繋ぐ役割を持ち、グルーヴを生み出します。DTM初心者はコードのルート音に合わせたシンプルなフレーズから始めましょう。ドラムのキックとタイミングを合わせると一気にまとまりが出ます。
ベース音源はシンセベースでもアコースティックベースでも構いませんが、低域がしっかり出る音色を選びましょう。
コードとパッドで楽曲の厚みを出す
コード進行を入力すると、楽曲の雰囲気が一気に広がります。ポップスなら「I-V-vi-IV」などの定番進行を使えば安定感があります。パッド音色を使って背景に敷くだけでも厚みが出るので、初心者でも簡単にプロっぽいサウンドに近づけます。
ピアノやストリングスの音色でコードを演奏してもよいでしょう。コード進行を決めることはメロディ作りの助けにもなります。
メロディの作成:モチーフ→展開
メロディは楽曲の顔となる部分です。DTM初心者は短いモチーフを作り、それを繰り返したり少し変化させたりして展開させるのがおすすめです。いきなり複雑にしようとせず、歌いやすいフレーズを意識しましょう。
リファレンス曲のメロディを分析し、リズムや音程の流れを参考にすると発想が広がります。シンプルでも印象的なメロディが作れれば成功です。
編曲(アレンジ)の基本
楽曲の大枠ができたらアレンジに進みます。イントロ、Aメロ、サビといった構成を整理し、楽器の出入りを工夫しましょう。例えば、サビに入る直前でドラムを抜いて盛り上げを作るなど、抑揚を意識すると聴きやすくなります。
DTMではトラック数が増えすぎがちですが、シンプルにまとめる方がまとまりやすいです。初心者は「引き算のアレンジ」を意識すると完成度が高まります。
ミックスの初歩(EQ・コンプ・リバーブ)
ミックスは楽曲を聴きやすく整える工程です。まずは各トラックの音量バランスを調整し、EQで不要な帯域をカットします。次にコンプレッサーで音の大小を整え、まとまりを出します。
リバーブを加えれば奥行きが生まれますが、かけすぎは注意です。DTM初心者は難しいテクニックにこだわるよりも「音量・定位・リバーブ」の3つを意識するだけで十分です。
マスタリングと書き出し:配信対応の音量設定
最後に仕上げのマスタリングを行います。全体の音量を調整し、ストリーミング配信に適したラウドネスに整えます。初心者は専用プラグインのプリセットを使うと簡単です。
完成したらWAV形式やMP3形式で書き出し、YouTubeやSoundCloudにアップしてみましょう。自分の作った音楽を公開することが、次の成長への大きなモチベーションになります。
学習の進め方と練習ロードマップ

30日で1曲完成を目指す学習プラン
最初の目標は「1か月で1曲を完成させること」です。毎日15分でもよいので、作業時間を確保しましょう。
1週目は機材やDAWに慣れる、2週目でドラムとベースを打ち込む、3週目にメロディとアレンジを加える、4週目でミックスと仕上げを行う、といった流れが理想です。短期間で「とりあえず完成させる」経験が大切です。
90日で3ジャンル(ポップ・EDM・Lo-fi)に挑戦
次のステップは、3か月で異なるジャンルに挑戦することです。ポップスでコード進行を学び、EDMでリズムとサウンドメイクを磨き、Lo-fiで質感加工を試すなど、幅広いジャンルを経験するとスキルが一気に広がります。
最初から完璧を目指さず「ジャンルの特徴を真似る」ことを重視すると、音楽の引き出しが増えてアレンジ力が身につきます。
180日で弱点克服ドリル(リズム・和音・サウンドメイク)
半年ほど経つと、自分の得意不得意が見えてきます。リズム感が弱ければドラムの打ち込み練習を繰り返し、和音に苦手意識があればコード進行を集中的に練習しましょう。
サウンドメイクに挑戦したい人はシンセサイザーの基礎を学ぶのがおすすめです。自分の弱点をテーマにした練習をすることで、バランスよく成長できます。
毎日の練習メニュー例と時間配分
毎日の練習は「インプット」と「アウトプット」のバランスが大切です。30分あれば前半15分を参考曲の分析、後半15分を実際の打ち込みに使いましょう。
余裕がある日は自分の曲を進め、短時間しか取れない日はドラムパターンの練習だけでも構いません。継続することが最大の上達法であり、少しずつでも習慣化するのが理想です。
サウンドメイク入門:プリセットから自分の音へ

シンセサイザーの基本構造(OSC/フィルター/エンベロープ)
DTM初心者が理解しておきたいのがシンセサイザーの仕組みです。OSC(オシレーター)は音の波形を作る部分、フィルターは音の明るさを調整する部分、エンベロープは音の立ち上がりや減衰をコントロールします。この3つを理解するだけで、プリセット音色を少し変えるだけでもオリジナルの音を作れるようになります。
プリセット音色を改造するステップ
シンセの世界は奥深いですが、最初はプリセット音色をベースに調整しましょう。フィルターを開けば明るく、閉じればこもった音になります。エンベロープを変えることで、パーカッシブな音やふわっと広がる音を作ることができます。小さな変化でも曲の印象が大きく変わるため、自分のイメージに近づける練習を繰り返しましょう。
定番プラグインと無料音源の活用
DTM初心者には、まず付属の音源や無料のプラグインを活用するのがおすすめです。ピアノ音源なら「LABS」、シンセなら「Vital」、ドラムなら「MT Power Drum Kit」など無料でも高品質な音源が揃います。有料音源に手を出すのは、基本を押さえた後でも遅くはありません。まずは身近なツールを使いこなすことが成長への近道です。
追加音源を買うタイミング
音作りに慣れてくると、よりリアルな音やジャンル特化の音源が欲しくなります。ただしDTM初心者が最初から高額な音源を揃える必要はありません。曲を何曲も完成させ「この音がどうしても必要だ」と感じたときが買い時です。無計画に購入するよりも、自分の音楽スタイルに合った音源を選ぶことで長く活用できます。
ジャンル別作曲レシピ(初心者でも“それっぽく”)

ポップスの王道コード進行と歌モノの作り方
ポップスは王道のコード進行を使えば、初心者でも簡単に「それっぽい」曲を作れます。代表的なのが「I-V-vi-IV」進行です。耳馴染みが良く、自然に歌メロをのせやすいのが特徴です。
ピアノやアコースティックギターで伴奏を作り、シンプルなメロディをのせればポップスらしい楽曲になります。サビでは音域を広げ、盛り上げを意識すると完成度が高まります。
EDMのビルドアップとドロップの作り方
EDMは展開のメリハリが命です。イントロから徐々に音を重ね、ビルドアップで緊張感を高めます。そしてドロップで一気に開放し、リズムと低音を強調します。
DTM初心者でもサイドチェインを使えば、キックに合わせてシンセやベースがうねるような迫力あるサウンドが作れます。シンプルなパターンでも、音の迫力でEDMらしさを演出できます。
Lo-fiヒップホップの質感とビート作り
Lo-fiはリラックス感やアナログ感が魅力です。DTM初心者はまずシンプルなドラムループを打ち込み、テンポを70〜90BPMに設定しましょう。
ピアノやギターのコードを使い、少しずらしたリズムで演奏すると“ゆるさ”が出ます。さらにテープノイズやビニールのパチパチ音を加えると雰囲気が一気にLo-fiらしくなります。難しい技術よりも「質感」を大切にするとよいでしょう。
ロック/バンド系DTM:ギター録音とリアルな音作り
ロック系のDTMでは、ギター録音が重要なポイントです。初心者はオーディオインターフェースに直接ギターを繋ぎ、アンプシミュレーターを使うのがおすすめです。
パワーコードやシンプルなリフを重ねるだけで迫力のあるサウンドになります。ベースとドラムをしっかり合わせることでバンド感が出やすくなります。録音が難しい場合は高品質なギター音源を活用してもよいでしょう。
ボカロ・歌声合成ソフトを使った楽曲制作
ボカロや歌声合成ソフトは、歌手がいなくてもボーカル入りの楽曲を作れる大きな魅力があります。初心者はまず既存のMIDIメロディを読み込ませ、歌詞を入力してみましょう。
発音やブレスの調整を工夫するだけで自然な歌声になります。ボカロ曲はYouTubeやニコニコ動画での発表にも適しており、自分の音楽を広めやすい環境が整っています。
サンプル音源・ループ素材の使い方と注意点

ロイヤリティフリー音源の利用ルール
DTM初心者が便利に使えるのがループ素材やサンプル音源です。しかし利用する際はライセンスの確認が必要です。ロイヤリティフリーであっても商用利用の可否や再配布の禁止など条件が定められています。
利用規約を読まずに使うとトラブルになる可能性があるため、信頼できる素材サイトを選び、ルールを守って使用しましょう。
サンプリングと著作権の基礎知識
既存の楽曲からサンプリングする場合は著作権に注意が必要です。短いフレーズでも無断使用は違法となるケースがあります。
DTM初心者はまず著作権フリーのサンプル素材や自作音源を活用しましょう。もし既存曲を引用したい場合は、権利者から許諾を得ることが必須です。クリエイターとして責任を持ち、正しい知識を持って制作を進めることが重要です。
安全に使えるおすすめ素材サイト
初心者におすすめの素材サイトには「Splice」や「Loopcloud」などがあります。月額制で膨大なループやワンショットをダウンロードでき、ジャンルごとの検索も便利です。
無料で使える「Freesound」や国産の素材サイトも役立ちます。安全なサイトを利用すれば、クオリティの高い素材を安心して活用できます。
よくある初心者のつまずきと解決法Q&A
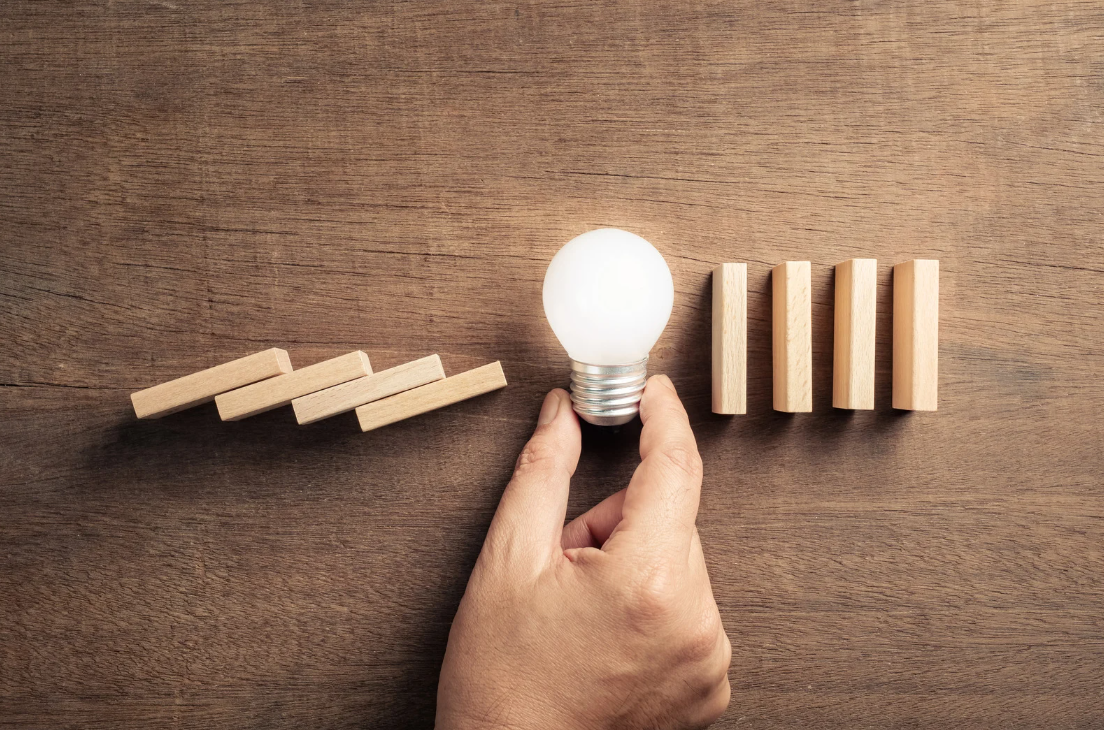
音が小さい/歪む → ゲインステージング
録音や打ち込みの際に音が小さすぎたり大きすぎて歪んだりするのは、ゲインステージングが原因です。入力段階から適切なレベルを確保し、トラックごとの音量バランスを調整しましょう。
レイテンシが大きい → バッファサイズ設定
演奏した音が遅れて聴こえる場合は、オーディオインターフェースのバッファサイズを小さく設定します。CPU負荷と音の遅れのバランスを取るのがコツです。
ノイズが入る → 接続や電源の見直し
録音時のノイズはケーブルや電源が原因の場合が多いです。シールドケーブルを変えたり、USBポートを別にすることで改善することがあります。
低音が暴れる → EQとモニタリング環境
低域が聴きづらい場合は、不要な帯域をEQでカットしましょう。また、ヘッドホンやスピーカー環境によっても低音の聞こえ方が変わるため、リファレンス曲と比較しながら調整します。
メロディが思いつかない → 発想法と参考曲活用
アイデアが出ないときは参考曲を聴いてモチーフを真似たり、リズムからメロディを作ったりする方法があります。DTM初心者は「完璧を目指さず真似から始める」ことを心がけましょう。
制作を効率化するワークフローと習慣

DAWテンプレートの作成
よく使うトラック構成やエフェクト設定をテンプレート化すると、制作スピードが格段に上がります。ドラム、ベース、コード、メロディの基本セットを作っておくと便利です。
キーバインド・ショートカット活用
DAWには数多くのショートカットが用意されています。再生、停止、コピー、ペーストなど基本操作をショートカット化するだけで作業効率が大幅に向上します。
リファレンス曲のAB比較
完成した曲をリファレンス曲と聴き比べることで、音量や定位の違いに気づけます。客観的な耳を養うためにも、常に比較する習慣を持つと良いでしょう。
バージョン管理とバックアップ術
DTMの制作ファイルは容量が大きいため、定期的に外付けHDDやクラウドにバックアップしましょう。バージョン管理をすることで、いつでも以前の状態に戻せる安心感があります。
ステップアップのための機材追加

インターフェース買い替えの目安
同時録音数を増やしたい、より高音質を求めたいと感じたらインターフェースの買い替え時です。入出力の多いモデルを選べばバンド録音にも対応できます。
マイク導入と宅録環境づくり
ボーカル録音をしたい場合はコンデンサーマイクの導入がおすすめです。自宅で録音するなら簡易的な吸音材を使い、環境ノイズを抑える工夫をしましょう。
モニタースピーカーと部屋の音響対策
ヘッドホンに慣れてきたらモニタースピーカーを導入しましょう。部屋の形や反響を考慮し、スピーカースタンドや吸音パネルで調整すると効果的です。
プラグイン購入の優先順位
有料プラグインを購入するならEQ・コンプ・リバーブ・リミッターが優先です。定番のプラグインは長く使えるため、セールを狙って少しずつ揃えるのがおすすめです。
学びを継続するための情報源とコミュニティ

YouTube/有料教材の活用
YouTubeには初心者向けのDTM解説動画が豊富にあります。無料で学べる一方、有料教材やオンライン講座は体系的に学びたい方に向いています。
DTMブログ・メディアのおすすめ
国内外のDTM専門ブログでは最新の機材情報や制作ノウハウが紹介されています。英語サイトも翻訳しながら読むと新しい発見があるでしょう。
オンラインサロン・SNSコミュニティ
DTMは孤独になりがちですが、オンラインサロンやTwitter、Discordのコミュニティで交流すると刺激が得られます。仲間の存在は継続の大きな支えになります。
モチベーションを維持するコツ
目標を小さく設定し、完成した曲をSNSに公開する習慣を持ちましょう。反応があると次の制作意欲につながります。
実践ケーススタディ

歌モノ楽曲の制作手順
リファレンス曲を参考にコードとメロディを組み立て、ボーカルを中心に楽曲を構築します。歌詞の響きを意識し、アレンジで抑揚を作ることがポイントです。
EDMトラックの制作手順
ドラムとベースでリズムの土台を作り、シンセサイザーで迫力あるリードを重ねます。ビルドアップからドロップへの展開を意識すると完成度が高まります。
Lo-fiビートの制作手順
ジャズコードを用いたピアノフレーズに、揺れるビートと質感加工を加えます。テープエフェクトでアナログ感を演出するのがコツです。
完成曲の公開と次のステップ

マスター音源の書き出しとラウドネス調整
配信用に書き出す場合は、音量基準(LUFS)を意識してマスタリングします。YouTubeやSpotifyに合わせた設定を選ぶと安心です。
配信サービス/YouTube/TikTokへの投稿方法
SoundCloudやYouTubeは無料で楽曲を公開できます。さらにTuneCoreやBIG UP!を利用すればSpotifyやApple Musicにも配信可能です。
SNSでの拡散とフィードバックの受け方
TwitterやInstagramに制作過程を投稿するのも効果的です。コメントや意見を受け取りながら改良していくと成長が早まります。
次の曲に活かす振り返り方法
完成後は必ず反省点をメモしましょう。「時間がかかった工程」「うまくいった工夫」を記録することで、次の曲がさらにスムーズに作れるようになります。
まとめ:DTM初心者が3か月で音楽を作れるようになるために

DTM初心者が最初に学ぶべきことは「完璧さ」ではなく「まず1曲を完成させる経験」です。本記事では、必要な機材選びからDAWの特徴、1曲完成までの流れ、ジャンル別レシピ、つまずき解決法までを解説しました。
3か月あれば誰でも1曲を仕上げられる力がつきます。音楽制作は継続が大切です。小さな積み重ねを大切に、自分だけの音楽を世界に届けてください。
関連記事
-

2026年2月16日
講師ブログピアノ教室の体験レッスンは何を見る?後悔しないためのチェックポイントと失敗しない先生の選び方完全ガイド
ピアノ教室の体験レッスンへ行く前に知っておきたい基礎知識 ピアノ教室選びで「体験」が最も重要視される理由 ピアノという楽器は、他の習い事と比較しても講師と生徒が一対一で向き合う時間が非常に長いのが特徴...
-

2026年2月16日
講師ブログ楽器演奏は最高の「脳の筋トレ」!ストレス解消から認知症予防まで驚きの効果を徹底解説
音楽を趣味にするメリットとは?人生の質(QOL)が劇的に変わる理由 日々の仕事や家事に追われ、ふと「自分を豊かにする時間が足りない」と感じることはありませんか。ストレス社会と呼ばれる現代において、心の...
-

2026年2月16日
講師ブログ音楽教室の振替は無料が安心!後悔しない選び方と回数・期限・注意点を徹底解説【2026年最新ガイド】
急な予定変更や体調不良…月謝を無駄にしたくない方へ 音楽教室に通い始める際、多くの方が抱く不安の一つが「急な予定が入ったときにレッスンはどうなるのか」という点です。仕事での残業や急な出張、あるいは自分...
Blog 講師ブログ
-
2026年2月16日
音楽教室の振替は無料が安心!後悔しない選び方と回数・期限・注意点を徹底解説【2026年最新ガイド】
急な予定変更や体調不良…月謝を無駄にしたくない方へ 音楽教室に通い始める際、多くの方が抱く不安の一つが「急な予定が入ったときにレッスンはどうなるのか」という点です。仕事での残業や急な出張、あるい...
-
2026年2月16日
ピアノ教室の体験レッスンは何を見る?後悔しないためのチェックポイントと失敗しない先生の選び方完全ガイド
ピアノ教室の体験レッスンへ行く前に知っておきたい基礎知識 ピアノ教室選びで「体験」が最も重要視される理由 ピアノという楽器は、他の習い事と比較しても講師と生徒が一対一で向き...
-
2026年2月16日
楽器演奏は最高の「脳の筋トレ」!ストレス解消から認知症予防まで驚きの効果を徹底解説
音楽を趣味にするメリットとは?人生の質(QOL)が劇的に変わる理由 日々の仕事や家事に追われ、ふと「自分を豊かにする時間が足りない」と感じることはありませんか。ストレス社会と呼ばれる現代...
Course コース一覧
Area スタジオエリア一覧
| 東京23区 |
|---|
| 東京23区外 |
|---|
| 神奈川県 |
|---|
| 千葉県 |
|---|
| 埼玉県 |
|---|


